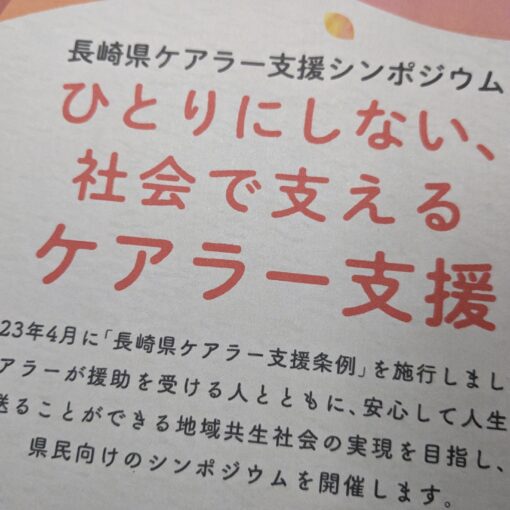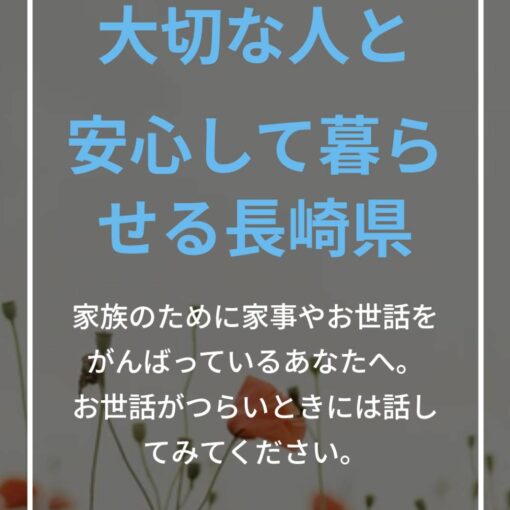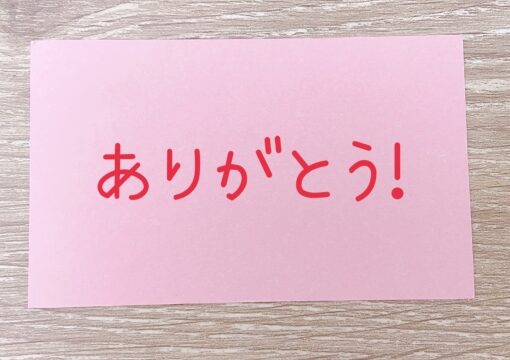「介護」や「介護者(ケアラー)」への意識が変化しています
都道府県や各市町など自治体における「ケアラー支援条例」の制定、それに向けた議論や準備のはなしを耳にすることが少しずつ増えてきているかと思います。
新聞やメディア等で取り上げられることも、ここ数年ますます増えてきました。
特に「ヤングケアラー」や「仕事と介護の両立」、また「ケアラー支援の法令化」などの話題もそうですね。
これまでは「介護」といえばいわゆる「高齢者介護」や「介護保険」の話題が中心であったかも知れません。
「介護」と聞いたときの上記のような印象も否めなかったと思います。
しかし、昨今は病気や高齢化問題に限らず、こども、子育て、教育、仕事(労働)、経済、外国籍、はたまた人生における選択など・・・多方面において、かつ多角的にそれぞれの課題の中のひとつに「介護」や「介護者(ケアラー)」のことが意識され考えられるようになってきています。
介護は誰にでも起こりうる誰にとっても「自分ごと」
「介護」や「介護者(ケアラー)支援」が以前に増して多方面で注目されるようになった今、改めて振り返っておきたい大切なことがあります。
「介護は誰にでも起こりうる自分ごと」という認識です。
また、いわゆる病気や障がいに対するケアだけが「介護」だという認識ももうひと昔前のこと。
今日では、日常生活のあらゆる「お手伝いの必要性」に対して「お世話」をすることと捉えるのが自然です。
このことからも「介護」という表現よりも「ケア」であり、介護者ではなく「ケアラー」と呼ぶことがしっくりくる。
そう考えるとなおさら、我々は性別も年齢も関係なく、また家族(親族)などに限ったことでもなく、日々の生活の中で「誰もが」「誰かの」「ケア(お手伝い)」をする可能性を秘めているのです。
まずはイメージしてみるところから
とは言え、未だに「介護」=「高齢になった親の面倒を見ること」であり、「介護者」=「高齢になった親を持つ子」であって、なおかつその子は「娘」ないし「嫁」で、夫婦間であれば「妻」であることがイメージとして根強いのかも知れません。
高齢夫婦の「夫」が、または子の中でも「息子」が、介護に携わっている状況をみると、なにか特別な印象を持つ。
長年の文化的な背景や、社会や人の固定概念はなかなか根強いものです。
しかし、もうそのような時代ではないとここは潔く思ってください。
ケアに限らず日常生活のさまざまなこと、例えば子育てであるとか、家事であるとか、結婚観や家族の在り方、そういったことが時代とともに変化していることは皆さんご承知なはずです。
これだけ多様性や平等であることが求められ、認められていこうとしている中で、いつまでも「ケア」だけが昔のままなはずはありません。
まずは一人ひとりが、自分の身近な大切なひとに「ケア」が必要になったら、「自分はどうするだろう?」「自分はどうしたいだろうか?」ということを丁寧にイメージしてみることからはじめるのはいかがでしょうか。
そのときに、「自分はできるだけプロに依頼しよう。」と考えて、そのための情報を集めておくことは、それも一つの方法だと私は思います。
なにも「自分ごと」=「自分でケアに携わる」ことをなによりお勧めするわけではありません。
そこは人それぞれですので、あまり重要ではないでしょう。
大切なのは、「(家族の)〇〇がやってくれるだろうから、自分には直接関係ない。」と、はじめからご自身を自ら蚊帳の外に置くのではなく、ケアに「(間接的であっても)関わる意識をもつこと」です。
必要な情報は自分自身でも取りにいく心構えを
都道府県や各市町におけるケアラー支援条例制定の広がりや法令化への議論など、今後、ケアラー支援に関する動きは国をあげてますます活発になるだろうと推測します。
特に、医療・福祉などの分野に限らず、こども(子育て)や労働の課題に「ケアラー」への取り組みが急務であることはすでに報道されているとおりです。
私が住む長崎県でも、令和5年4月に長崎県ケアラー支援条例が施行され、初年度はその「推進計画」が策定され、先日公表されました。
少しずつ、しかし確実に前に進んでいることを県民の一人として嬉しく思います。
長崎県に限らず国や地方自治体は、今後さまざまな角度から多様な属性のケアラーに関する動きを起こしてくるはずです。(起こさなくてはいけない時にきています)
そして、前述のとおり、我々は一人ひとりが誰しもケアラーになる可能性があり、ケアは「自分ごと」です。
そこで次に重要なのは、ケアに関する自分が欲しい情報は「自分からも」取りにいくこと。
取りにいく意識を持つことです。
ケアを自分ごととして考えそこからまずはイメージすると、自分自身が知らないことや疑問に思うことなども出てくるでしょう。
知らないことや疑問を「解決」するためには「情報」が必要です。
今はまだ具体的なケアの状況が目の前になくても、イメージを実現させるための「情報」をすでに持っているかどうかで、実際にケアがはじまったときのスタートがだいぶ違います。
ケアがはじまってからでは遅い・・・とまでは言いませんが、かなり違ってくると思います。
実際にケアがはじまってからでは、「ケア」はあなたの情報収集を待ってはくれないからです。
また、ケアやケアラーに関する国や地方自治体の動きがいくら進んでも、あなたがそれを知らなければすぐに活用できません。
ケアに限らず何にしろそうですが、行政側から発信される情報において、その発信方法や周知には限界があります。
いくら発信する媒体を工夫されていても、100%ではない。
黙って待っていたら、向こうから入れてくれるだけの情報しか入ってこないこともあり得る、それが現実です。
ケアはいつはじまるかわかりません。
でも、だからこそ「備えておくこと」が大きなポイントであり、自分の自己実現のためには「人任せにしない」ことです。
もちろん、ケア自体は悪いことでもありません。
しかし「愉快」で「楽しい」ことばかりかと言えば、それもどうでしょうか。
ケアは生活の一部であり、人生の中でつながっている
あなたは、「ケアラー」としての自分をどう考えますか?