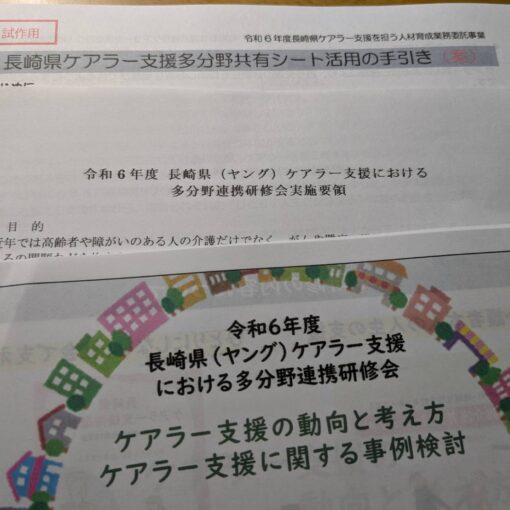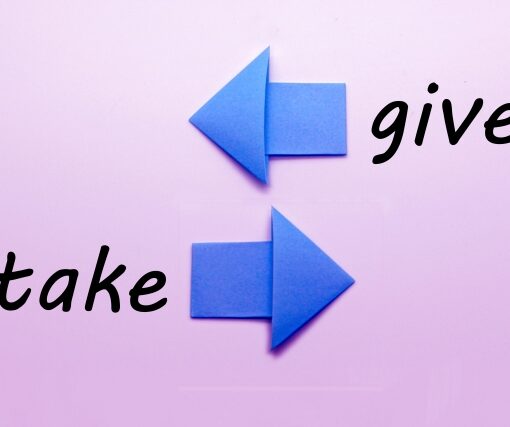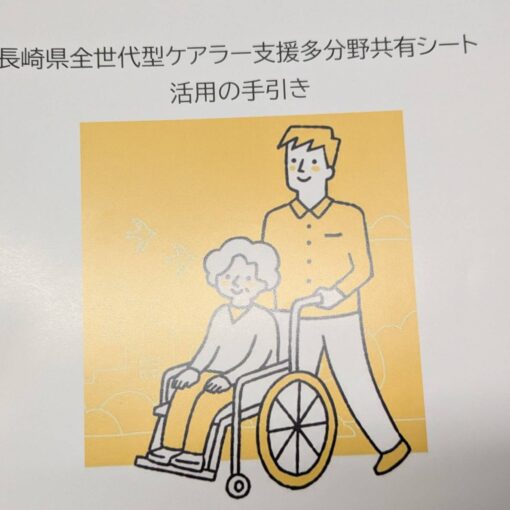ケアラー支援条例制定への動きが進む背景・・・
全国でケアラー支援への動きが活発になってきています。
政府は、ヤングケアラーについて、文科省および厚労省連携のもと実態調査や調査後の課題分析、対応策への取り組みなどを各自治体へ急がせています。
大人ケアラーにおいても、「介護」の課題に対し政府が動き出したのは安倍政権のころですから、実はなにも最近の話ではありません。
国の動きの背景には、残念ながら介護やケアラーに関する痛ましい事件が起こり、問題が浮き彫りになり、結果政府が介護を「社会問題」だとようやく認識したことも理由の一つに上げられると思います。
介護離職、介護殺人、子どもの貧困、教育の不平等さなど、これらにまつわる実態が「ひっ迫した家族介護」や「介護者の孤独」に関連することであると、少なくとも政府は認識しています。
国は動いています。
つまりは、必要なところに予算を付けています。
ケアラー支援を志す者としてはありがたいことですが、動き出すのはある意味当然なのです。
地方自治体におけるケアラー支援への体制整備はもはや必須
ヤングケアラーにしろ、19歳以上の若者ケアラー、大人ケアラーにしろ、地方自治体が「それは都会で起こっている問題」「うちの町には、ヤングケアラーなんていない」「うちの町には、そんな介護問題なんてない。」とは、もはや言えないでしょう。
都市部も地方の町も、家族(家庭)の在り方や市民一人ひとりの生き方、そして子育てや教育においても社会全体が変わってきているのに、ある一部の町の「介護」だけがずっと昔のままなんてそんなわけありません。
人々も、人々の生活も変化してきているのです。
「介護」に関しても、同じように変化しています。
そう考えると、ケアラー支援は都市部でも地方の町でも早急に対策が必要なはずです。
どの都道府県や市町においても、ケアラー支援への取り組みを考えていかれるべきで、その必要性を今ようやく考えはじめているのは遅いぐらいだと思います。
前述した「それは都会で起こっている問題」「うちの町にはヤングケアラーなんていない」という自治体の考え方は、とても危険で間違っています。
まだこれからのところは、介護やケアラーに関する痛ましい事件が起こる前に早く動き出してください。
行政にありがちな体制整備は、・・・少しズレている?
結果、行政が「ケアラー支援に対する体制整備」を考え動き出すときにありがちなのが「ハード面」の支援です。
もちろん大事です。
活用できるサービスや支援がたくさんあると、ケアラーとしてはそれはもちろん助かります。
ケアラーにとって介護は「生活」であり、日常の中の「一部」ですから、応援や気持ちだけではありがたいけれど具体的な解決にはなりません。
しかし、一方で懸念されるのは、「サービス(支援)の押し付け」です。
配食サービスでの食事の提供、ヘルパー派遣、日用品の支給・・・もちろんどれもあると便利なのですが、それらが、さもそうすることだけで「ケアラーの課題が解決されるでしょう!」と行政や支援者サイドからケアラーに押し付けられる形になれば、それはちょっとズレているかも知れません。
「体制整備を行った」「支援に取り組んだ」という、行政側の実績はわかりやすく残るでしょう。
しかし、それ以上にもっと大事なことが先にあると思います。
ケアラーに「情報」と「選択肢」、そして「権利」を。
自身も一人のケアラーであり、ケアラー支援を志す者として申し上げます。
まずは「聴いて」欲しいのです。
ケアラーとはこういう人とか、こういうことで困っているはずとか、そういう一括りに捉えられるのではなく、「一人のケアラーである私の声」を聴いて欲しいのです。
ケアラーは「介護」を通してさまざまな課題を抱えた状態にあり、日々たいへんな毎日を送っているかも知れませんが、決して「弱いひと」ではありません。
往々にして、自分で考え、比べ、選ぶことができます。
強いて言えば、今、そしてこれまでは、「情報」や「選択肢」がなかったのです。
「情報」や「選択肢」が欲しいということや、欲しいと言ってもいいことを知らなかったのです。
これまでは、そのような漠然と「知らされていない環境」「気持ちを伝えられない環境」に置かれていたことが多かったのではないかと思います。
そうであればなおさら、「情報」を得て、自分で「比べて」、自分で「選ぶ」ことをしてもいいとケアラーに伝える支援介入がまずは必要ではないでしょうか。
ケアラーの選択肢を増やすためにもハード面への体制整備はもちろん大事です。
しかし、それと並行して、ケアラーの心の声を聴くことはもっと大事だと思います。
そして、なにより、ケアラーがその「心の声」を安心して発信してくれる信頼できる環境づくりはとても重要なのです。