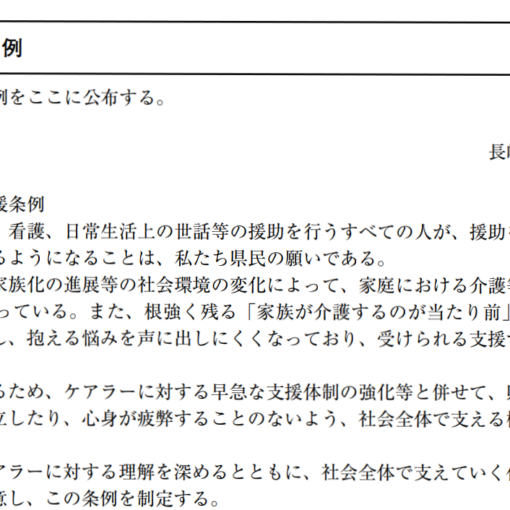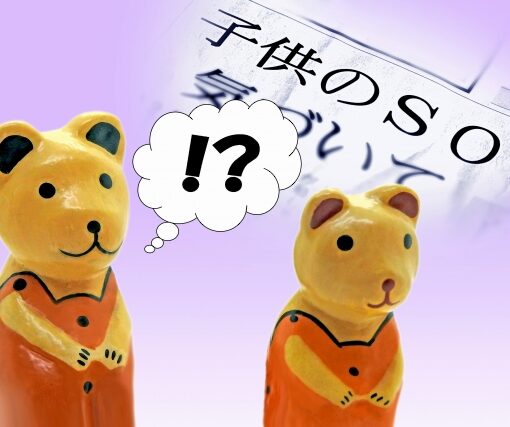措置から契約への移行と「介護費用」
「ケア(介護)が必要になった」と聞いて、まずどのようなことに不安を感じますか?
ケアは往々にして病気や障がいをきっかけに必要となるわけですから、もちろん要介護者となった親族等のお体のことをまずは心配されるかも知れません。
されど、往々にして、(ケアラーとなった)あなたはその後すぐに要介護者にこれから必要な「ケア」の「具体的なこと」を考える時間が訪れるでしょう。
家族などにケアが必要になったとき、周囲はケアラーをそうそう悠長に過ごさせてはくれません。
ケアラーはそういつまでも悲観に浸ることもできず、現実的な判断や選択を迫られることになりがちです。
そこで必ず出てくるのが「介護費用」についてです。
高齢者福祉も障がい福祉も、一部をのぞいて「行政措置」から「契約」の時代です。
つまり、ケアサービスを利用するにあたり当然その「費用」がかかります。
この点について、考えなければならない時間が必ずあります。
介護費用って、家族だから負担するのが当然?
親のことだから、自分は家族だから、その介護費用を一手に引き受けて負担するべきだ。
今どきのケア(介護)にはお金がかかるから、仕方ない。
本当にそうでしょうか?
自分自身がケアラーであった過去を振り返りあらためて思うのは、ケアに対する費用負担は、ケアを必要とする要介護者本人に対する収入でなるべく賄うよう考えるのが鉄則だと私は思います。
年金など定期的な収入で賄えない場合は、要介護者本人の預貯金をケアのために切り崩し補填することも当然含まれるでしょう。
つまり、これから必要な介護費用を考えるうえで、なるべく要介護者本人に「経済的自立」をしてもらうようにまずは検討していく。
当然、法的には家族間の「扶養義務」についてまったく無視することはできませんが、可能な限り要介護者本人の収入で介護費用を用意することが、ケアラーにとっても、要介護者本人にとっても、今も将来的にも望ましいでしょう。
何にしろ生活にお金がかかる昨今。
この視点は、いつまで続くかもわからないケアに向き合っていくうえで、ケアラーと要介護者双方にとって、お互いの生活のため、はたまた人生においてもとても重要です。
要介護者(家族)の経済状況を知っていますか?
介護費用を要介護者本人に負担してもらうためには、要介護者となった本人の経済状況を「預貯金もふくめて」大まかにでも日頃から確認しておくことが重要です。
そのためには要介護者本人と事前に「情報共有」しておくことが必要になってきます。
また、ありがちなのが「いざという時のために、貯金があるから大丈夫!」
大切な心がけではありますが、これは大きな落とし穴でもあります。
重要なのは「使える預貯金がある」ことです。
金融機関の口座から引き出すこともできない預貯金があっても、いざ必要となったときにはなかなかすぐには役に立ちません。
だから日頃からの「情報共有」であり、家族とはいえ、そのためにも「信頼関係」が大切なのです。
ちなみに、個人的には、亡くなっときのための「葬祭費」を確保しておくぐらいなら、ご健在のうちの介護費用や生活費に充てる方がお金の使い方としては有益だとも思います。
いまどき、葬祭費はどうとでもできる手段がありますが、介護費用こそ準備するものに余裕があればあるほどいい。
ケアサービスをお金を払って購入する時代ですから、サービスの選択肢が確実に広がります。
ケアは「生活」だからこそ
ケアは生活の中の一部。
生活にはお金がかかるもの。
中でも介護費用は、いつまでどれぐらい必要か、どういう風に変わっていくか、先の見通しがなかなか立ちづらいものです。
また、介護費用は社会保障の変化からも影響を受けることがあります。
その点においては、メディア等でも報道されているとおり、先の見通しが良いとはとても言えない状況があります。
ケアがはじまった最初のころに、あまり深く考えず取り急ぎ介護費用を全面的にサポートするような走り出し方をしても、それが数か月、数年、もしくは十数年続いていくかも知れない。
そうなったとき、要介護者の介護費用だけではなく、ケアラー自身の生活を何らかの形で困窮させる可能性も出てくることが十分考えられます。
ケアラーにとって、要介護者にとって、双方に幸せな形とはとても思えません。
要介護者が病気や障がいを負いながらも「長生き」してくれることに、そこにいてくれることに、言葉には出さずとも先々の不安を覚えるようでは、結局どちらもつらいと思います。
ケアにまつわるお金の話はとても大切で、現実的に判断する必要がある。
ケアの専門家や窓口に相談しながら、どうすれば要介護者本人の収入や預貯金で介護費用が賄えるか、支払った費用が戻ってきたり、そもそも支払いを減額できるような諸手続きはないか、情報収集することをまずは試みてください。
情報はこちらから求めていかなければ、あちらから都合よくやっては来ません。
子どもだから、家族だから・・・といった固定概念にはじめから振り回されずに、なるべくお互いに「経済的自立」ができる介護体制を整えることを意識しましょう。