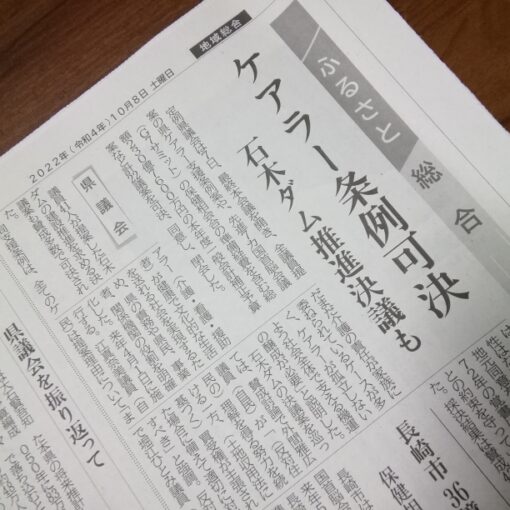リーダー研修に参加しました
私は「全国介護者支援団体連合会」に所属しています。
「全国介護者支援団体連合会ホームページ」 ↓ ↓ ↓
介護者支援を全国に波及します! – 全国介護者支援団体連合会
全国各地の「ケアラー支援の活動団体」または「ケアラー支援活動に関心のある方」などが所属している全国組織です。
連合会の活動の中で年に数回、所属している皆さんがWEB上で集まり意見交換や情報収集なども行っています。
先日、主にケアラー支援活動団体のリーダーさんたちが集う「リーダー研修」が開催され、ファシリテーターとしてケアラー友達(「ケア友」と私は呼んでいます)と一緒に参加しました。
テーマ「仕事と介護の両立のリアル」です。
ケア友さんのお話、そして行動力にあらためて感動!
具体的な内容は個人情報保護の観点からここでは割愛しますが、お仕事とケアについて、家族への想いや、ご自身の考えなど、これまでやこれからのことをお話してくださいました。
「自分の経験が誰かのためにもなれば・・・」まずはケア友さんのこの心意気に感謝と敬意をお伝えしたいと思います。
【ありがとう!】
ケア友さんとはケアラー支援活動を通して以前から知り合いです。
今回のこの企画を準備するにあたり内容を打ち合わせしたり、お互いの考えや想いをあらためて共有することができ私自身も本当に勉強になりました。
そして、なによりケア友さんの「行動力」に心から感動!
かれこれ二十数年前からのケア生活。
福祉施策にしろ、仕事とケアにしろ、ケアにまつわる諸制度等が「ケアラー」の視点で(も!)騒がれるようになってきたのはここ数年のこと。
「介護は情報戦」だとも言われています、しかし「どうしたらそのケア情報が手に入るのかわからない」状況は二十数年前も最近もそう大きく変わらないと思いますし、以前はよりそうだったかも知れません。
いくら「ケアは誰にでも起こり得る」とはいえ、なかなか黙って待っていてもあちらから積極的には近づいてきてくれないのが「ケア情報」です。
現在でも往々にしてそうでまだまだ課題でしょう。
そう考えると、ご自身のケアがはじまった二十数年前の当時からケア情報を「ご自身で」必死に取りに行き、そして「困ってる」「〇〇のことが大変だ」ときちんとご自身の言葉で発信してこられたそのお考えと行動力は本当にすばらしいです。
もちろんケア友さんにもいろいろな場面があったこれまでだったのではとお察ししますが、ともあれ「求める情報」「求める生活」を「自分で取りに行く」ところに立ち返るエネルギーや思考は同じケアラーとしても尊敬します。
(よろしければ、こちらも ↓ ↓ ↓)
誰もがケアラーになる可能性のある時代—自分に必要な情報は「自分からも」取りにいく!~自分の人生は自分で守りましょう~ | 社会福祉士事務所まきの木|毛利真紀|
自分自身を振り返る
ケア友さんのお話を聴いていく中で、ケアラーである自分自身のこれまでもつい振り返ったり思い出したりします。
ケア生活がはじまった当時、私にはケア友さんのようなエネルギーも考えもありませんでした。
このブログやSNSで、その他いろいろな会議や研修等の場面で、呪文のように「ケア(介護・お世話)は他人事ではない」と発信しています。
だからこそ「ケアについて備えましょう」と言っています。
備えるというのはつまり「イメージ」し「(必要だと思われる)情報収集」をはじめておくということです。
ケアについて「知っておく」「考えておく」ということです。
もし「ケアを理由に【大切な何か】をあきらめなければいけない」状況が、事前の「備え」で少しでも回避することができたらその方がいいと思うから。
私は実際にケアがはじまると多くの場合「ゆっくり考える時間がない」ことを知っているからです。
でも、ケア生活がはじまった当時の私はまったくそのような自分ではなく、起こった状況に対して苦しいとか、しんどいとか、なぜ私ばかりが~とか、そんなどうしようもない歯がゆさとも虚しさとも言えない複雑な気持ちでボロボロでした。
今思えば恥ずかしいですが、これが私なのです。
そしてこの経験が今の私の「原動力」でもあります。
支えたり、支えてもらったりしながら「自分」も大切に。
ケア(介護・お世話)は生活の中にあります。
生活の一部です。
生活者として誰にでも起こり得る「ひとつの状況」に過ぎない。
もちろん、ケアが悪いわけでもありません。
ケアを「必要としている人」のことを否定や批判するつもりもまったくありません。
私もいずれいつかは何らかの形で「ケアを受ける立場」になるだろうとも思っています。
また、ケアであろうが、その他の何であろうが、ひとの生活や人生の中で時に「変化」が起こるのは当然であって、その「変化」が良いことであったり、そうでないことであったりする。
そして、誰もひとりでは生きていない。
みなさん、家族であっても、そうでなくても、誰かを支えたり誰かに支えてもらったりしながら日々を送っていると思います。
人が人を想いながら、同じように自分自身も大切にしていく社会であってほしい。
自分自身が「自分」に対しても「愛情」と「責任」を一緒に持ちましょう。
自分自身がケアラーになった場合をイメージし、ケアに備える。
それはケアを受ける人のため(だけ)ではありません。
「あなたのため」なのです。