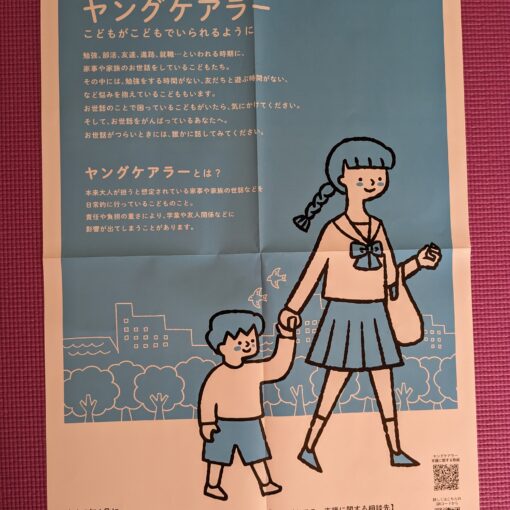家族が集まる季節だから・・・
新しい年になりました。
コロナはまだまだ収束する気配が見えませんが、wihtコロナでの生活に人々の意識も環境もだいぶ変わってきました。
今年のお正月はあちこちでふるさとへ帰省される方々がさらに多かったようです。
今回は、この季節恒例?の「介護について家族で話をすること」をテーマにお話しします。
*過去の「介護について家族で話をすること」シリーズはこちら ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
介護について家族で話をすること | オフィス紗代|毛利真紀|長崎県佐世保市の社会福祉士事務所 (nagasaki-officesayo.com)
そもそもなぜ?この季節恒例なのか。
勘違いを防ぐために一言お断りすると、あくまで私の個人的な意見ですが、親やきょうだいなど家族の介護が差し迫ってない方にとって、年がら年中「介護」のことを考えるなんて、実際に現実的ではないと思っています。
それはそれで、ある意味「普通」で「一般的な感覚」だろうと。
そして、夏のお盆も家族によっては必ずしも年間行事としてあるものでもありません。
しかし、新年(お正月)はおそらくどこの家族にもある一年の節目のときで、家族がお顔を合わせたり、連絡を取ったりする季節かと思います。
なので、元旦から・・・とは申しませんが、親やきょうだいに久しぶりに会ったり、話をしたり、そんな時間の一コマでこのテーマを考えてみるのはいかがでしょうか?というご提案です。
大切なこと、その①~あなたの気持ち~
上記「介護について家族で話をすること(2022年1月9日付)ブログで、私は家族介護に対するご自身の考えをまとめておく上でまず重要なのは、「ご自分で介護するか、しないか。」だと述べています。
その点は、今も基本的に変わりません。
日頃からも、要介護者の支援プランを作成する方、ケアマネジャーさんや相談支援専門員さんなどには、まず支援者らから見て「主介護者」だと決められがちな家族にその点を十分に意思確認することが大事だと訴えています。
「介護するか、しないか。」を、自分以外の人、他の家族や親戚の人、要介護者の支援者らに、いつの間にか決められる。
介護を担うかどうか、どれぐらい担えるかどうかも検討しないまま、勝手に担うものだと決められてしまうことは、絶対に避けるべきです。
家族介護経験者だからこそ申し上げますが、この現象は家族の介護がはじまったそのときにとてもありがちな空気感で、家族介護初心者が自身の意思さえ見失いがちになることは往々にしてあります。
当然のことながら、ご自身で介護を担うことを避けるべきだと言っているのではありません。
それもまた自由です。
しかしながら、それを決めることは絶対にあなた自身で行われるべきだと思います。
自分で決めたことでないと、少なからずいつかどこかで後悔したり、はがゆい想いをされることになるかも知れません。
そのときの空気感に流されるのではなく、「家族介護」に対するご自身の意思は、ご自身の中にしっかりと確認し続けておくことをお勧めします。
もちろん、途中で気持ちが変わっても構わないのですから。
大切なこと、その②~家族の気持ち~
親やきょうだいのこと、お金や生活習慣や考え方などを知っておくことは大事です。
もちろん、先の「あなた自身の気持ち」を伝えておくことも大事です。
家庭(家族)の現在の状況に限らず、仕事や子育てなど予測できることがあればこれからの予定もお互いに知っておくとより良いかも知れません。
一度に全部とは申しませんが、少しずつでもご家族でお互いに共有することをお勧めします。
重要なのは、家庭(家族)内で「なすりつけあう」「押し付けあう」ことをしないこと。
家族の誰かから誰かに一方的に介護を担うことを求めたり、逆に、考えや想い、ご自身の予定とは裏腹にやみくもに引き受けるような結果にしないことです。
少なくとも、そういう空気感を通してしまわないことです。
それぞれに考え意見があってもそれらがすべて完璧に叶えられるものでもない、家族間で調整がきかないことだってあり得ることを、頭の片隅に置いておきましょう。
こういうときこそ、介護保険などのいろいろな社会保障を、または支援サービスを活用することを、この時点で選択肢の一つに考えておき提案してみましょう。
ご自身で介護できる、またはそうしたいと確信が持てず、なんだかモヤッとするのであれば、それは後々たぶん後悔したり困ったりすることになりがちです。
今はまだ想定であっても「対応できない(かも)」「むずかしい(かも)」という気持ちは、お互いに伝えあっておいてもいいと思います。
事前のこの時点で、むしろその確認こそが大事です。
そのためには「介護保険」や「障がい福祉サービス」、「仕事と介護の両立に関する諸制度」、これらの情報に介護がはじまる以前から敏感になっておかれることがいかに重要かということになります。
近い将来尋ねるかもしれない地域包括支援センターや行政窓口の確認も、共有しておけるといいですね。
エンディングノートを作成しているから大丈夫?
ここで家族介護ではないのですが、私が業務として担っている成年後見の同業者から伺ったお話をご紹介します。
最近、「エンディングノート」を作成する方が増えているようです。
「終活」という活動(心構え?)もよく耳にするようになりましたね。
一人ひとりが自身のこれからや気持ちに向き合うのは、良いことだと私も思います。
しかし、このエンディングノートなのですが、例えば一度作成されたその内容に絶対的な法的根拠が伴うものでもない。
あくまでそれを書かれた、準備されたご本人の「それを書いたとき」「準備したとき」の意思や想いを確認するものであると、改めて認識しておかれた方がよろしいかと個人的には思います。
公証役場等で作成されたいわゆる「遺言」のような、きちんとした公的な文書ではありません。
ご本人が「要介護状態になったら、介護施設で介護を受けることにしたい。」なんて書いてあっても、いざそのときになって家族や支援者らがそのように進めようとしても、本人は「施設入所なんて、いやだ~!」と、話がひっくり返ることも往々にしてあるわけです。
自然なことですが、人の気持ちは変わりますから。
エンディングノートや終活が、何もいけないのではありません。
大切なことは、内容を共有し、定期的に見直し、「今」にアップデートされていることかと思います。
そもそも論で・・・介護は「一方的なもの」ではありません。
要介護者と介護者がいる話です。
準備も「お互いに」「一緒に」がポイントだと思います。
家族が「介護」や「家族のこれから」に対して何を考えたり思ったりしているか、やはり「伝えあうこと」は大事です。
一度や二度ではなく、「定期的に」です。
家族がエンディングノートを作成していることすら知らなければ、元も子もないですしね(笑)