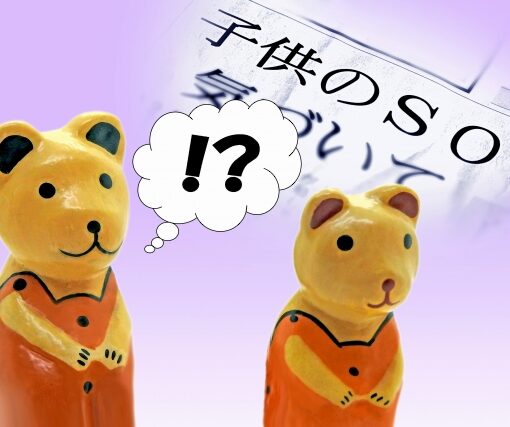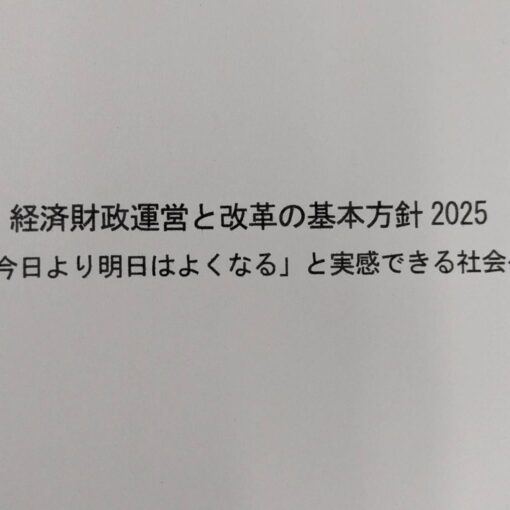「ケアラー支援」と「仕事と介護両立支援」は別物・・・誰が、どの立場から考えることでしょう?
私は、「ケアラー支援」と「仕事と介護の両立支援」は「介護」や「介護者」というキーワードで繋がってはいるけども根本的には「別物」だと考えるタイプです。
それは、なぜか。
「ケアラー支援」にしろ、「仕事と介護の両立支援」にしろ、それらにまつわる立場や捉える視点が、人によってそもそも違うからです。
その人の立場が、ケアラー(家族介護者)なのか、介護業界の支援者なのか、働く人(労働者)なのか、経営者(雇用主)なのか・・・
抱える悩みも、考えなければいけないことも、それぞれの立場から取り組まなければいけない、整えなければいけない課題となることも、当然違ってくる。
そして、どこか一か所の官公庁や行政窓口だけ、何某の制度だけ、どこか、どれかだけが特化して考えれば整うというものでもありません。
多機関からの動き、取り組みが必要です。
実際に、それはこれまでのケアラーや働く介護者を取り巻く環境をみていても、明らかです。
「介護」や「介護保険」の担当課だけが取り組んで、整うものでもなかったでしょう。
「ケアラー支援」と「仕事と介護の両立支援」は別物・・・ケアマネジャーさんが取り組むべきなのはどちらですか?
「ケアラー支援」は「ケアラー支援」です。
そして、あくまで「仕事と介護の両立支援」は労働者の「キャリア支援」だと私は考えます。
しかし、この考え方は、実はなかなか伝わらないことが多いです。
「介護」のことでしょ?
だから、「介護の課題(問題)」なんでしょ?
じゃあ、「介護保険制度」でしょ?
と言えば、「ケアマネジャーさん」でしょ?
う~ん・・・そうでしょうか・・・なんだか、モヤッとします。
はっきり申し上げます。
ケアマネジャーさんに、「キャリア支援」は難しくないですか?
というよりも、そもそも論で、それをすべき立場でしょうか?
ケアマネジャーさんに課せられていることと言えば、「ケアラー支援」の方だと私は思います。
本来のお仕事であるケアマネジメントを通して、「ケアラー支援」に取り組むのがケアマネジャーさんではないでしょうか。
つまり、「仕事と介護の両立」は、労働者と経営者(雇用主)が抱える「労働契約(または環境)」の課題ですよね。
介護保険業界、特にケアマネジャーさんらが、「ケアラー支援」に対し動き出してくださっていることは嬉しく思います。
しかし、ご自分たちの立場や分野から、何をすべきで何ができるのかを、冷静に捉えなければ、せかっくの取り組みも中途半端なものになってしまう恐れがあるのではないでしょうか。
「ケアラー支援」と「仕事と介護の両立支援」は別物・・・じゃあ、仕事と介護の両立支援の問題ってなに?
また、シングル(独身者)ケアラーの支援活動をしていると、なおさら、当然のように、
「じゃあ、もちろん!『仕事と介護の両立』については問題視してますよね?」
なんて、メディアの方などから特に言われがちです。
まあ、してるかしてないかと言えば、してます。
社会全体の中でみれば、してる方だと思います(笑)
しかし、先でも述べましたように、それらを一緒くたには捉えていません。
問題視と考えるとすれば、ケアラーでかつ働く介護者が、「仕事と介護の両立」と「雇用契約は一旦解除してでも、今は家族の介護選びます」という、どちらについても選択肢や選択権、強いてはそれらに対する保証や環境がまだまだ整ってないってことは問題かなと思います。
どちらにしろ、今はまだまだ一個人の自己責任であることが大きいです。
少なくとも、これまでなんて往々にして自己責任でした。
つまり、「選択肢が見えないまま、そうするしかないという思い込みだけでする介護離職」は、問題です。
そして、「再就職もキャリア形成もあとでいくらでも考えるけど、今は絶対的に家族介護に比重をおきたい。しかしそうは言っても、あとでいくらでも考えられないキャリ形成の現実や、そもそも論でどうやって生計を立てていくのかという経済的課題が突きつけられるがゆえに、やりたい介護もできずに無理くりモヤッと働くしかない状況」
も、どちらにしても問題だと考えます。
社会や社会人としての義務と、一市民としての選択の自由と、民主主義としての保証と環境整備のバランス。
それが、日本はまだまだこれからだと思います。