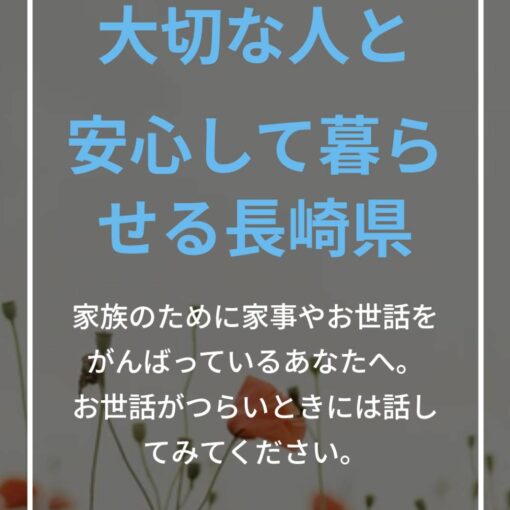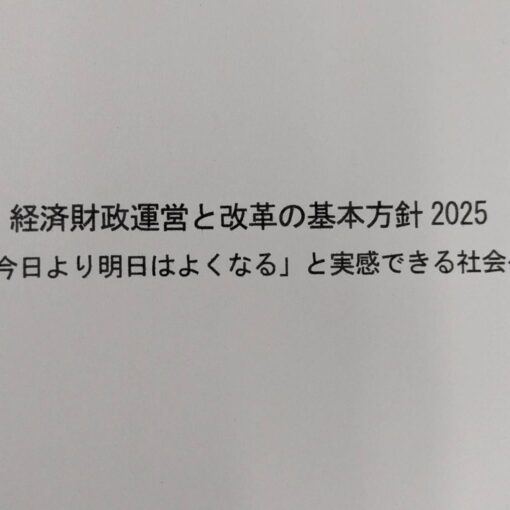ケアラー支援条例制定の最近の動き
全国でケアラー支援条例制定への動きが徐々に高まっています。
埼玉県入間市では、令和4年6月21日、「ヤングケアラー支援条例」が全会一致で可決されました。
ヤングケアラー支援に特化した条例は全国で初めてです。
さっそく、同年7月1日から施行されます。
また、同じく埼玉県さいたま市では、「さいたま市ケアラー支援条例」が同年6月24日に市議会で全会一致で可決されました。
ケアラー支援に関する条例は、政令市では初めてのことです。
埼玉県は全国ではじめて「ケアラー支援条例」を制定された県としてケアラー支援業界では有名ですが、その後の動きについても、他都道府県および市町村に対し、よい影響力を持ち続けて頂きたいです。
条例制定・・・だから、ひとまず安心ですか?
さて、そのように少しずつではありますが、昨今、ケアラー支援条例制定への動きが活発になってきています。
しかし、一方で、条例制定後の経過を見ているケアラーの意見には、あまり注目されていないのではないかという懸念もあります。
私は、細々とではありますが、仲間にも助けてもらいながら介護者支援を10年間志してきました。
ご縁あって、全国の同じ志のみなさんともネットワークを作っています。
そんなケアラー支援仲間の皆さんが、最近口々にご意見されること。
それは、「ケアラー支援条例があれこれ進んでるけど、・・・それで、その後はどうなったの?」
要するに、「条例はできたけど、そこまででケアラー支援体制整備の動きが終わっているのではないか?」ということです。
このご意見は、ケアラー支援条例制定にご尽力頂いた議員さんや行政のみなさんには耳が痛いかも知れませんが、ケアラー支援活動を行っている多くの人たちの声だと私は感じています。
本当に大事なのはその後
もちろん、条例制定後についても、引き続き頑張っておられる都道府県や市町村、および議員さんもいらっしゃることかと思います。
しかしながら、ケアラーである当事者はやはり率直で正直です。
ケアラー支援条例は、自分たち当事者が直面している介護の課題や支援活動に直結します。
条例が制定され、その旨のリーフレットができ、世帯に配布されたり、公共機関の情報ラックに置かれているだけでは、それは納得できません。
「まつりごとに終わってしまった」・・・つまり、「自分たちの生きづらさを政治利用されてしまった」という印象すら残しかねないのです。
大事なことは、ケアラー支援条例が制定され、その内容がより当事者にとって有意義なものであること。
有意義なものであり続けるように、さらにアップデートされていくことです。
ケアラー支援条例はできてからが、より重要なのです。
アップデートに多角的に取り組む重要性と効果
ケアラーが抱える課題や置かれた環境も様々ですし、昨今、特に多様化している傾向にあります。
ヤングケアラーも、18歳以上のおとなケアラーも、いずれもその課題は複合化されており、一言で支援と言ってもなかなか単純なものではありません。
そこを単純に捉えすぎると、支援があたかも「行政措置」のようになってしまう恐れさえあります。
そうならないためにも、包括的な視点からの支援が重要かつ必要なのです。
そのためには、支援に他職種、多方面からの「連携」が有効であると私は考えます。
条例の内容を見直していくとき、行政側としてはおそらく「有識者(学識経験者)」と呼ばれるメンバーを構成されるかと思います。
それも、もちろん間違ってはいません。
ただ、ここで忘れて欲しくないのは、「ケア(介護)」は「生活」であり、「ケアラー支援」はケアラーの「人生の支援」であるということです。
行政の担当課と有識者で、机上で、データ分析をして、本当に実質的で有効性のある課題解決策を模索しようとするのには、いささか限界があると思います。
条例制定前だけではなく制定後にも、ぜひ当事者の生の声を活かす方法をご検討頂きたいです。
また、ケアラー支援に精通した事業を行っている企業の参画も、有効な手段の一つではないでしょうか。
ケアラー支援を中身のある効果的なものとして持続させていくためには、それが出来る者たちが携わるの一番です。
官民一体となって取り組むことも、必要な場面もあるかと思います。
当事者は、「条例ができたらそれで満足」ではありません。
ずっと活用できる、当事者のための条例でなければ意味がないのです。