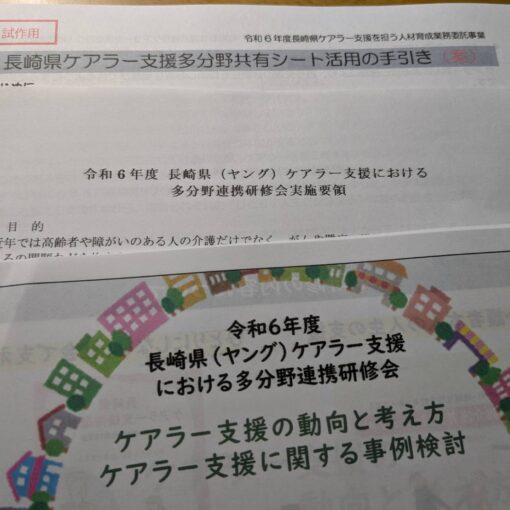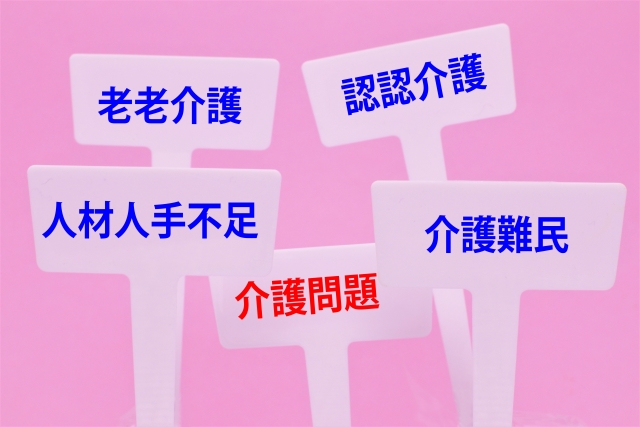
ケアラー支援は「高齢者介護」だけの課題ではない
全国でケアラー支援条例制定への動きが、国をあげて進められていることをこれまでお伝えしてきました。
はじめに、最近、ご質問を受けることが多いので、ここで改めて確認しておきたいことがあります。
「介護」と言えば「高齢者」・・・つまり、ケアラー支援も「介護保険」の分野だけが抱える課題のようについイメージされがちかも知れませんが、それは違います。
ケアラー支援は、高齢者介護に限った話ではありません。
ケアラー支援の対象となるのはケアしている家族だからです。
介護を必要とされている方の年齢層で、ケアラー支援を分類することは難しいでしょう。
また、昨今、生活の中で家族の誰が誰をケアしているかという状況も様々になっています。
ひと昔前のように、「妻が・・・」「長男の嫁が・・・」なんてことも、必ずしもそうではないのが最近の家族介護です。
ケアラーが多種多様だということは、ケアラーが抱えている状況の課題(困りごと)も就労、経済、子育て、ヤングケアラーであれば教育など、多岐にわたります。
家族とは言え、一人の人格者としての「権利」も含まれてくるかも知れません。
「ケアラー支援」と聞いてまず何が思い浮かびますか?
前述のとおり、今我が国ではヤングケアラーをはじめ、ケアラー支援の対象となる方は幅広い年齢層です。
ケアラー支援は、もはや国が抱えている喫緊の課題となっています。
すでに条例制定が進んでいるエリアでは、また条例制定がまだ進んでいないエリアでも、ケアラー支援への動きは少しずつ始まっていますが、国の施策として進められているということは、主として行政機関や事業の委託機関でアプローチの支援体制が組まれていることも多いと思います。
先日、ケアラー支援に携わる委託機関のスタッフの方から、このようなご意見を耳にしました。
「困っているのだから、早く解決してあげなきゃ。」
「そのためにも、一刻も早く相談窓口につないであげなきゃ。」
・・・なるほど。
確かに抱える課題が早々に分析出来て、然るべき対応窓口に繋がって、ケアラーの困りごとがいち早く解決されるといいですよね。
目指すところは、そう間違ってはいないと思います。
ただ、一度立ち止まって、ご自分たち支援者の「動き方」を振り返ってみてください。
その支援のスピード感は、手段は、本当にケアラー自身が主人公になっていますか?
答えはすでにケアラーの中にあることも
行政機関、その委託機関がケアラー支援に取り組むとき、はじめにケアラーに対するアセスメントを行うことは必須です。
「困っているはず!」
「助けて欲しいはず!」
それは必ずしも間違ってはいないかも知れませんが、支援の専門機関ともなればその判断となる根拠は確実に抑える必要があります。
そもそも、命に関わる緊急事態でもない限り、ケアラー支援が「行政措置」になってはいけません。
それは、ケアラーにとって、そしてケアを受けている要介護者にとっても、下手すれば信頼を得るどころか心を閉ざしてしまうことにもなり兼ねないからです。
自身も一人の当事者として申しますが、そもそもケアラーも情報は欲しいですが、それらを選択するのは自分自身でありたいと思うのではないでしょうか。
ケアラーは何某困ってはいるかも知れませんが、弱い人ではありません。
まずは要介護者中心ではなく、ケアラー中心のアセスメントをはじめに丁寧に行いましょう。
それは、つまり「ケアラーの声」をきちんと聴くことから始めるということになるはずです。
声を聴くためにはケアラーに想いを話してもらわなくてはいけませんよね。
そのために大切なのは、まずケアラー自身に「あなたのことを気にかけている。」という支援者の想いが伝わること。
要介護者だけではなく、「ケアラーのあなた」も同じくらい大切に想って気にかけていることを知ってもらうことだと思います。
本当は何に困っていてどうしたいのか、何を望んでいるのかは、実はケアラーの心の中にすでにあることも少なくありません。
ただ、ケアに明け暮れる日々で、自身の想いを話していいとも思っていないケアラーもいるかも知れません。
聴いてもらえるわけないと、思い込んでいるケアラーもいるかも知れません。
ケアラーに心を開いて話してもらえるようになること、ケアラーの声を丁寧に傾聴することが、ケアラー支援において一番初めに必要なことではないでしょうか。
支援者側が、支援者本位に急がないことは重要だと思います。
行政も、市民活動もどちらの働きかけも大事
私はケアラー支援を志して今年で丸10年になります。
支援と言いましても、ケアラーのつどいの場を開催するという、言ってしまえばそう派手な活動ではありません。
集いの場は、つまりは「ケアラーのしゃべり場」です。
普段、家庭や職場、ケアをしていない(知らない)友人等には話しづらいような介護にまつわる想いを吐き出してもらう場所の開催を10年間同じ志の仲間とぼつぼつやってきました。
いろいろな媒体を活用し、ケアラーの想いを代弁し世の中に発信する活動も個人的には続けていますが、同志の仲間と一番大切にしていることは、実はこの集いの場の開催なのです。
そしてその多くの時間が、ただただそこに集うケアラーの声を聴くことです。
10年間、ずっと大切にしてきました。
そして、10年間続けてきましたが、それでもまだまだこの時間は足りていないと私も仲間も感じています。
ですから、これから先も、長崎県に、全国に、ケアラー支援条例が制定されても、この活動は続けていかなければと思っています。
冒頭でも述べましたが、昨今、対象となるケアラーは多種多様です。
行政支援(条例、法制度等)とピアカウンセリング(市民活動)の双方の協力で、ケアラー支援がより良いものになっていくことを願います。