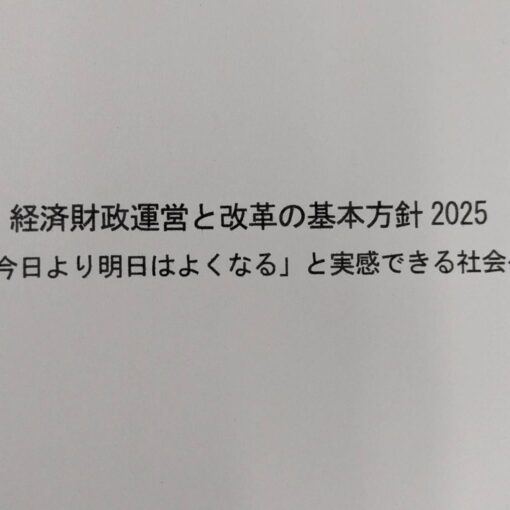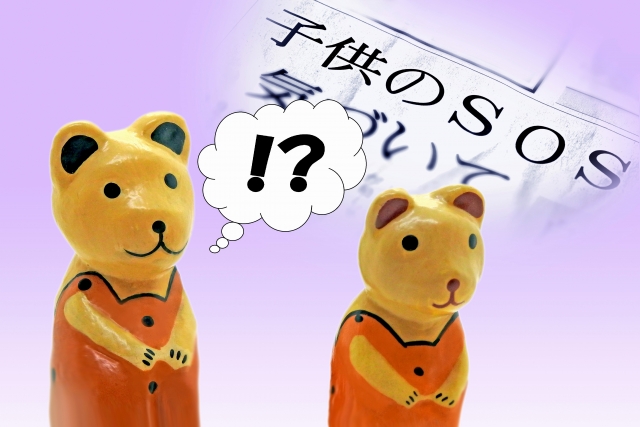
ヤングケアラーの実態調査
最近、特に「ヤングケアラー」と呼ばれる年齢が若い家族介護者さんのことが、たびたび新聞やテレビ番組などでも取り上げられています。
文科省からも、昨年、各都道府県(市町)へ、ヤングケアラーに関する実態調査を行うよう指示が出されました。
各都道府県、各市町でも、ヤングケアラーの実態把握はもちろんのこと、支援策の構築や具体的な対応が早急な課題となっています。
日本ケアラー連盟をはじめ、全国の介護者支援団体や弁護士会など、多くの団体や組織がこの動きに注目されています。
以前からヤングケアラーはいた・・・はず。
介護者支援を考える一人として、政府や各都道府県(市町)のヤングケアラーに対する動きや、動き出してくださったことについては、率直に嬉しく思います。
ただ、ここ最近になって世間の多くの方はこの「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたちや若い家族介護者さんのことを耳にしたり、そのような介護(生活)状況をメディアなどで知った方も多いのではないでしょうか。
私は、肌感覚ではありますが、かなり以前からその状況にある小学生や中学生、十代の子どもたちや若い方々はいたと思ってます。
なので、ヤングケアラー支援への取り組みは、もっと正直に言うと、介護者支援を考える上で対応としてはかなり遅い方ではないかと思います。
それだけ、彼らの現状がなかなか正確には表に出てこない(こなかった)ということなのかも知れません。
元?ヤングケアラーだった私からのお願い
私の家族介護がはじまった当初。
要介護者である家族が50代後半、私は20代後半でした。
その当時、「ヤングケアラー」なんて呼ばれていたかどうか自身の記憶は定かではありませんが、当時は若いケアラーだった者の一人として、ヤングケアラーへの支援を考える方々、支援者さんたちにどうしてもお伝えしたいことがあります。
それは、ヤングケアラーに対する支援だからこそ言ってはいけない「禁句」です。
以下は、私が先日、自身のFacebookにアップした文章です。
とても、とてもお伝えしたいことなので、ここにも記したいと思います。
(言葉が「乱暴」なところがありますが、どうしても伝えたい想いを込めた結果です。どうかお許しください。)
令和3年2月16日毛利真紀Facebookより
ケアラーへの禁句っていくつかあると思いますが…
特にヤングケアラーさんに対して「若いから大丈夫![]() 」はありがちだけど絶対にいかんと私は思います。
」はありがちだけど絶対にいかんと私は思います。
だって、その「若さ」が悩みどころの一つでもあるわけですから。
苦しさの要因の一つでもあるわけですから。
そんな声かけ、一ミリも救われない。
私は、家族介護が始まった当初、かれこれ、もう十数年前…
その当時ヤングケアラーという呼び方があったかどうかそれはあまり覚えていませんが、たぶんギリギリ、今で言うヤング〜に入ってたかと思います。
親は50代後半、私は20代後半…
ざっくり年齢だけで言えば、一般的な家庭よりも一世代前倒しで家族介護がはじまった私たち親子の年齢をどれだけ恨めしく思ったことか…
「大丈夫…って、なんや。 ナントカの一つ覚えみたいに、言ってんじゃねえよ。」
とか、
「60代の子どもの90代の親が、少々ボケたからって、……………だからどうした?」
とか、
感謝も労りも、へったくれもない、どうしようもなく冷えきった暗黒の時代だった。
ただ、この当時の心境は本当に正直にまぎれもない事実であって、やれ福祉だの、支援だの、今はイッパシなことをうんちく言ってますが、私というニンゲンの中にこんな心理が少なくともその当時あったことを隠したりせずに、今とこれからは生きたいと思っています。
私だから、伝えられることであって、伝えないといけないことだと思うから。
「介護」を本気で変えていきたいのです。