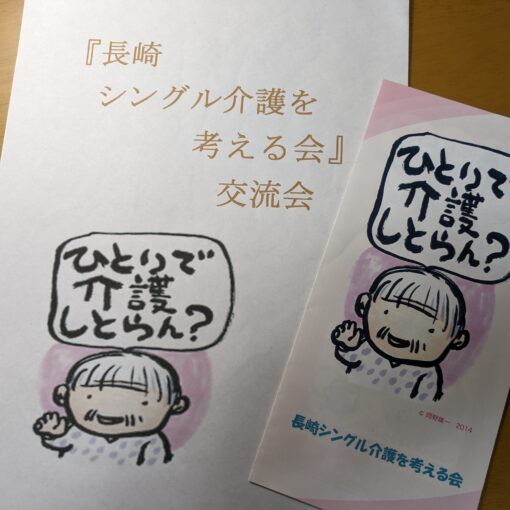活動再開しました!
「長崎シングル介護を考える会」という市民活動団体に所属しています。
(長崎シングル介護を考える会HP http://singlekaigo.jimdo.com/)
2012年からなので、この活動も早いものでかれこれ8年。
私と他に3名の世話人さん、そして会員さんたちとぼつぼつマイペースに活動中~です。
主に、ケアラーカフェ(みたいな集いの場)を開催し、情報交換、日頃の想いの吐露、シングル(独身)介護者の声の発信を主たる活動にしているのですが、
昨今のコロナ禍の中、我々の活動もなかなか思うようにいかずしばらく直接的に集まることはお休みしていました。
そして、県内での感染状況が若干落ち着いてきて活動自粛への県や市町からのお達しも幾分ゆるやかになり、
先日、ひさしぶりに少人数ですが集まることができました。
再会できた幸せ
この世の中ですので、あれこれ使えばふだんWEB上でつながることは出来はします。
しかし、やはり直接顔を合わせ、それぞれに想いやどこにもぶつけようのないモヤモヤを聞いたり、聞いてもらったりできる、
一緒に笑ったり、泣いたりできる時間はかけがえのないものであることを、深く痛感した数か月でした。
もちろん、この先、感染が終息に向かうことを願います。
しかし、我々のような活動も「新しい活動スタイル」を見出していかないといけないのかも知れませんけどね。
ほんとうに、いつ何が起こるか、降りかかってくるかわからない世の中になったものです。
いつ我が身に降りかかってくるかもわからない・・・「介護」もそう(涙)
介護、そして介護者について考える
私は、自身もシングルケアラーであって実際に介護離職も経験しました。
その後、社会人としてどう「仕事」と向き合うか。
仕事と介護の、そして自身の私生活との両立をしていくか。
親が病気し、介護がはじまって十数年、ずっと考えてきたし、自分もあれこれ経験してきました。
私たちケアラーのこと。
そして、我々が生きている社会のこと。
当事者として、社会福祉士という職業人として考えてきました。
そんな中、ひとつ自分なりにたどり着いたことがあります。
介護者一人ひとりが持っている「選択肢」についてです。
介護者一人ひとりにきちんと「選択肢」は与えられているか
つまりは、必要な情報はきちんと届けられていて、世間や周囲の人たちの意見に左右されることなく、介護者自身が比べて、選んで、決めているかどうか。
もっと正確に言うと、
そもそも、きちんと情報を得る機会があるべきで、介護者自身も「情報を得る」権利があること、そこから自覚があるかどうかということです。
ケアラー支援の主催者にもいろいろな意見や考え方があるかも知れません。
ただ、私は、まず「選択肢」。
選択肢があることはまず絶対で、民主主義の基本。
極端なことを言えば、
介護離職して介護に専念することをその介護者自身が吟味して選んだのであれば、それはそれで一つの答えだと思うので尊重します。
プライバシーなこともありますので詳細は控えますが、私のまわりにも、実際に、
自身や家族の経済的なことも含めてきちんと計画し、自身の年齢、要介護者とのこれから残された時間、あれこれ考えつくした結果介護離職し、介護を含めた自身の生活を大きく見直した方がいます。
実は、しばらく悩まれていた時間があることも知っています。
あれこれ方法を試みて、模索している時間があったことも。
ただ、考えに考えた末にそうされたので私は良かったと思っていますし、当人も、「今の生活スタイルが気に入っている。」と堂々と言われているので、こちらもホッとします。
一人ひとりが「介護」を自分ごとと受け止め、早々にアンテナをはること。(社会人として受け身ではいけません。それはあなたが損しかねません。)
介護や介護生活にまつわる「選択肢」がもしご自分にない、または少ないと感じたら、専門家に相談し求めること。(相談先の専門家に、あなたのことを「介護の社会資源」だと思われる前に、まず「介護について自分で考えて、決めたい」という意思表示をきちんとしましょう。)
行政の担当者や地域包括支援センターなどの職員さん、ケアマネジャーさん、企業内における自社の従業員の働き方を考える担当課の方々、介護や介護生活にまつわる「選択肢」の情報提供が十分にできているか、必要な方にきちんと届いているか意識と取り組みを改めてお願いします。
そもそも・・・
介護には、自分でするかどうか、したいかしたくないか、そこから「選択肢」があるはずなんです。