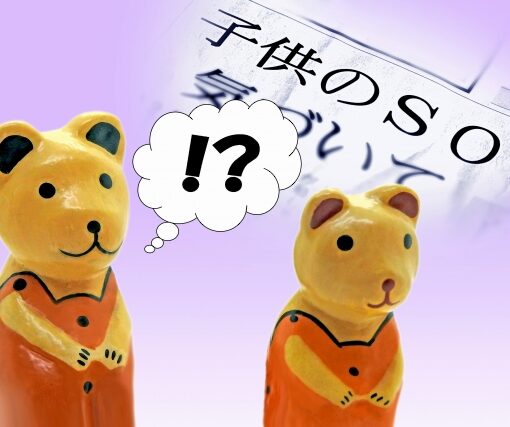一人のケアラーである私だからこそ
日頃は、独立型社会福祉士として後見業務を中心に、細々とではありますがいろいろな活動をしながら個人事務所を経営しています。
その一方で、ケアラー支援をライフワークの一つにしています。
ケアラー支援・・・つまり家族介護者さんに関する活動です。
きっかけは、私自身、30代の頃から家族の介護に向き合うケアラーだからです。
実際には、その家族も今年2月に看取りお空に見送りました。
ですので、ケアラー支援においては、自身が社会福祉士という福祉の専門職であることは厳密にはさほど関係ありません。
まあ、国や社会が抱えるケアラー支援への課題を考える際には、少なからず専門性とか専門的視点が入らないこともないとは思いますが、基本的には、その職業がゆえにこの活動をしているわけではありません。
一人のケアラーである自分だからこそできる活動があると思っています。
ケアラー支援条例制定への我が国の動き
今、全国で「ケアラー支援条例」制定に向けた動きが活発化してきています。
埼玉県をはじめ、すでに条例が制定されている都道府県や市町も少しずつ増えています。
そもそも「ケアラー」という言葉や表現が、最近はニュースや新聞等のメディアでも取り上げられることが増えてきましたね。
「ヤングケアラー」などが特にそうかも知れません。
私はすでに大人ケアラーなのですが(笑)、この世間の動きを見て、10年間ケアラー支援活動に携わってきた者としての率直な感想は、国も都道府県も「こども」が絡みだすと動きが早い!ということです。
それは現実的にそうなるのかも知れません。
社会って、そういうものかも知れません。
ただ、もう何年も前からケアラー支援にしろ、仕事と介護の両立にしろ、介護離職にしろ、その課題に声をあげてきた方々がいて、そして最近注目されている「ヤングケアラー」も、ここ2~3年のうちにはじめて登場した子どもたちではないということは、頭の片隅に必ずおいていて頂きたいと思います。
つまり、我が国のケアラー支援条例制定に向けた動きは決して早いものではなく、ケアラー支援の先進国などからしてみれば日本は十分遅れているのです。
長崎県ケアラー支援条例制定にむけて
とは言いましても、遅れているのであれば急がなくてはいけませんし、とにかく急いで頂きたいのが当事者であります。
先日、とあるご縁を頂き、自民党長崎県連の勉強会(意見交換会)に参加しました。
自民党県連の議員の皆さん、県庁の関係部署の職員さん、そして介護にまつわる市民活動団体の皆さんといろいろな意見交換ができ、私自身も大変勉強になりました。
私は、所属する長崎シングル介護を考える会の世話人としても、また一人のシングルケアラーとしても、主として「仕事と介護の両立」や「介護離職」に対する想い、そしてケアラーの心の支えでもある(と思っている)ケアラー支援活動について、意見させて頂きました。
こうして、直接的に意見や想いを伝えられる場を設けて頂いたことに、まずは感謝したいと思います。
いかんせん、・・・なかなかありませんから(苦笑)
議員さんから、令和2年度から準備をはじめ、今年度の条例制定を目指しているとのご説明がありました。
一人のケアラーとして、ケアラー支援に携わる者として、この動きはすなおに嬉しく思います。
まずは0から1にすることの重要さ
こういうとき、時々耳に入ってくるのは、「あくまで市民活動なのに、結局行政に利用されているのではないか」とか「政治家に利用されているのではないか」みたいなアンチな?ご意見です。
少なからず、聞こえてきますよね(苦笑)
まあ、いろいろな捉え方や考え方がありますので、それもまた世の中でしょう。
いろいろなご意見があることはそれもまた理解しますが、個人的には別にいいと思っています。
目指すゴールが一緒であれば。
その過程に、何某思惑があってもそれはある意味お互い様です。
各々の立場からお互いを尊重でき、各々の芯がぶれなければいいと思っています。
結果、お互いにウィンウィンであればいいし、使うも使われるも自身の心の持ちようです。
私、先ほど、遅れているのであれば急がなくてはいけませんし、急いで頂きたいのが当事者だと申しました。
今、一人のケアラーとして、一番大事だと思っているのはそこなんです。
長崎県ケアラー支援条例を「制定させること」なんです。
何かを新たに作り出そうとするとき。
0だったものを1にする作業が最も大変で難しいのではないかと個人的には思っています。
とりあえず出来上がった1のものを2や3や4により良く改正していくことももちろん大事なステップです。
しかし、まったく何も形のない0からのときよりも動きやすさはだいぶ違うはずです。
当事者として、とにかく早く1になることを願っていますし、1ができなければその先もないのです。
今後も、県内外のケアラー支援条例の動きに注目していきたいと思っています。