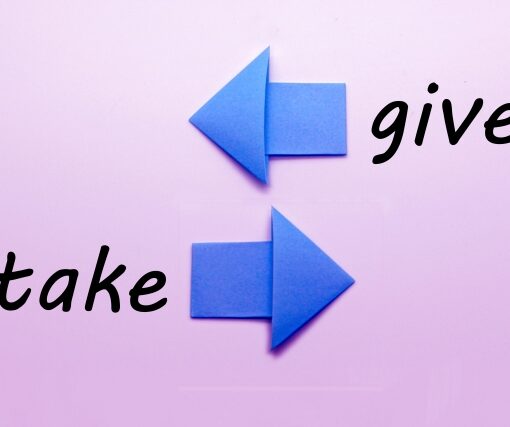介護の話?我が家にも必要?
2022年がスタートしました。
連日のコロナ報道で、またも世間は騒がしくなってきていますが、今年のお正月は、2年ぶりの帰省などができた方も多かったのではないでしょうか?
ちょうど、家族が集まったり、連絡をしたりするこの時期でもありますし、本日は「介護について家族で話をすること」についてお伝えしたいと思います。
みなさんは、親やきょうだいと「介護」のお話をされたことはありますか?
もし、今現在、またはこれまでに、親や祖父母、もしくは家族の誰かがご病気や障がいをお持ちでしたら、介護(看護)にまつわる何かしらの話をされたことはあるかも知れないですね。
今回は、もうすでに「介護」がはじまっている家族ではなく、これから「いつはじまるかはわからない家族介護の話」についてです。
中には、「介護の話なんて縁起でもない!」とか、「親から『年寄り扱いするな!』って怒られます。」というご意見もあるかも知れません。
確かに、介護は、何かしらのご病気や障がいを元に起こるわけですから、そう考えると喜ばしいものでもありませんし、どちらかと言えば、可能な限り避けて通りたいことかも知れません。
では、「介護」ではなく、こう考えてみるのはいかがでしょうか?
「毎年、一年ずつ年を重ねていく家族それぞれのこれからの話」
親や家族のこと、把握してますか?
ズバリ!「介護」には備えが必要です。
私の経験上、備えのない介護は苦労の連続です。
よい介護生活のスタートなんておそらく難しいです。
そして、介護の備えと一言で申しましても、その内容はたくさんあります。
介護にまつわる情報しかり、お金のことしかり・・・
私は30歳のころから十数年、若くで病気した親の介護をしています。
自身の経験をもってみなさんにお伝えしたいと思うこと。
それは、備えの中で大切なことの一つに、「親、きょうだい、家族のことをきちんと知っているかどうか」ということです。
親やきょうだいの生活状況、経済的なこと、そして大事なことは「気持ちや考え方」です。
それは例えば、「お金の使い方や価値観」「生活の中で重要だと思うこと」「病気や健康に対する考え」「自身の最期のときについて」・・・など。
ちなみに、私は、両親の経済的な状況は父の成年後見人になってから、はじめて知りました。
「まあ、二人が困らないぐらいはあるんだろう。」ぐらいにしか思っていませんでした。
成年後見人になって職務上確認する中で、また母から話を聞くことで、父(と母)のお金に対する考え方や希望、これまでのやりくりのことを知りました。
延命措置などについては、たまたまですが父がまだ病気する以前に、父の親(私の祖父母)が病気した際の父の考えを覚えていたので、一応知っています。
いずれにしても、もう少し、父の口から考えや想いを聞けていたらよかったなと今は思います。
また、想いや状況の確認については、親だけに限らず、一緒に家族の介護状況を抱えることになるであろう、きょうだいなど他の家族についても、大切になると思います。
事前に意見交換をしておくことは、その後の介護生活にとって大きいはずです。
そして、自分自身の生活のことも
もう一つ、大切なことは、自分自身にもし介護者生活が始まった場合のことを想定し、家族介護に対するご自分の考えや想いをまとめておくことです。
ここで、私はまず重要だと思うのですが、なかなか伝わりづらい部分でもあるので、ハッキリ!申し上げます。
まず最初に、なるべく考えをまとめておくべきことは、そもそも「ご自分で介護するか、しないか。」です。
こういうと、「そんなこと、今、決めれな~い!」と思われるかも知れません。
しかし、「介護に備える」ことを始める前にここをある程度ハッキリ明確にしておかなければ、「備え方」がだいぶ違ってきます。
そして、もう少しお話しすると、この意思表明は、介護がはじまってから登場する要介護者の「支援者」と言われる人たち(ケアマネジャーさん、介護事業者さん・・・etc)たちの支援体制への心構えや介護のプランニングにも影響します。
介護業界の方々からの批判を承知で申しますと、黙っていると勝手に「主たる介護者」にされてしまいがちです。
書類の中に、「そう、書いていいです。」なんてあなたは一言も言ってないのに、「キーパーソン」などと書かれてしまうかも知れません。
まあしかしながら、そうは言っても、人によってはあまりに極端すぎるかも知れませんね。
例えば、親と同居している場合などは、一緒にそこで生活しているわけですから、キッパリ!と線引きも難しいかも知れません。
では、少なくとも、ご自身の生活の中で、たとえ介護がはじまっても「譲れないもの」だけは確かめておくことをお勧めします。
仕事、子育て、夫婦のこと、勉強している何か、趣味のこと・・・
ご自身にとって、「それを犠牲にしながらの介護者生活は難しいです。」と思う何かがあれば、そこだけでも考えておくと、先にも述べました「それを介護で犠牲にせずに守っていくための介護の備え方」が見えてくるかも知れません。
必ずくる将来のために
大切なのは、親やきょうだいと、ご自身のことも含めて想いや考えを日頃から伝えあって、意思確認をしておくことかと思います。
なぜなら、往々にして「介護は突然はじまるから」です。
病気や障がいは突如家族やご自身のもとに舞い降りてきます。
そして、それは残念ですが、どうしようもなく起こることがほとんどです。
誰のせいでもない辛さがありますが、家族もご自身も誰だって一年に一つずつ年齢を重ねていくこと、老いていくことだけはわかっています。
そして、いつか最期のときを迎えることもそうです。
また、いざ介護がはじまったあと、要介護者となった家族と、しっかり深い話や意思確認ができるかどうかもわからないのです。
お正月や連休など、親やきょうだいと会ったり、連絡をとることが多い時期に、あえて頭の片隅にこのことを考えておかれるといかがでしょうか。
ちなみに、私は専門職後見人として後見業務を行っておりますが、自身のクライエントさんと最期の時について話をするきっかけに、お盆の頃や、または亡くなったご家族のお話を聞く際にあえて話題にしてみたりしています。