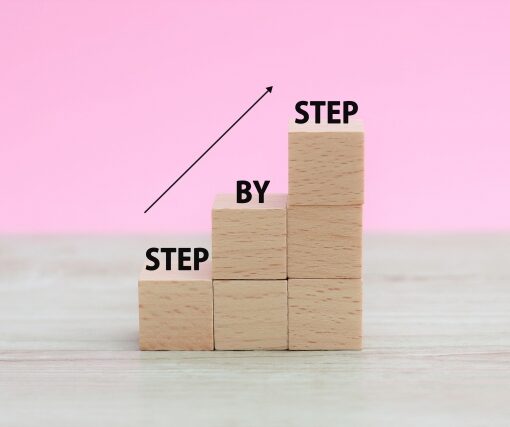日々の仕事の中で
勤務していた地域包括支援センターを退職し、独立起業しました。
自分のやりたいことと働き方、ちょっと大きく言えば人生を考える中で、勤務先という組織に所属する必要もないと思いました。
正確には、もうないかな・・・と。
労働者としての年数の概ね半分はサラリーマンでやってきたし、自分の年齢とこれからを考えたら、今がいいと思いました。
ただ、社会福祉士として、主たる業務は福祉の相談支援専門職であるわけで、独立しようが組織に勤めようが、基本的なところは変わらないと思っています。
そして、今、起業し自分で仕事をするようになって、改めて見えてくることもあります。
相談窓口につなぐ
ありがたいことですが、少しずつ、ひょっこりお電話をくださって相談を受けることが増えてきました。
相談というよりも「こういう状況で、こういう風に考えるんだけど・・・間違ってないよね?」という専門職の方からの確認とか、
「ちょっと、聞いて欲しい・・・。」という福祉職の方からの愚痴などもあります(笑)
基本的に一般市民の方からのご相談に対しては、私は内容を伺ってから然るべき窓口や専門職につなぐことにしています。
対応すべき窓口があるのに私が個人的に受ける必要はないし、各窓口の職員さんには職務を全うして頂きたいので。
現実的な話をすると、そうする方が相談者にとっても概ね無料です。
もちろん、何故その窓口に対応してもらうべきなのかご説明しますし、ご紹介する際に間に入ることもあります。
「私(毛利真紀)に紹介されたと言っていい。」とも付け加えるようにしています。
自分なりに、責任は持ちたいです。
そして、可能であればその後の経過(解決)も気になります。
趣味がおせっかいなので(笑)
窓口を選べない事実
そんな中、何かしらの窓口をご紹介するにあたり、実は困ることも。
いくらこちらが経験上自信を持ってご紹介しても、ときに相手の方から返ってくる言葉が・・・
「その窓口なら知ってる。でも、・・・そこに相談したって。」
非常に残念です。
ですが、きっとこれまでに何かしらご相談しても、納得のいく答えや対応が得られなかったのでしょう・・・とお察しします。
しかしながら、この現状を受け、我々専門職は立ち返るべきことがあると思います。
多くの場合、相談者は、ご自身が利用するべき窓口が一方的に決められています。
市役所や区役所、町役場などの行政窓口、地域包括支援センター、社会福祉協議会・・・
「あなたはここ〇〇町の住民さんですから、利用できる相談窓口はここです。」
市町の規模にもよりますが、例え同じ市内でも、隣り合わせの〇〇町と△△町の地域包括支援センターが違う場合もあります。
私は、なにも町単位で窓口をわけてあることを否定しているわけではありません。
システム上、致し方ない場合もあるでしょう。
ただ大切なのは、相談者(利用者)にとって、同じ看板を掲げている窓口なのにたくさんあって、その上、ご自身が利用するべき窓口が一方的に決められているということを、意識して業務にあたっているかということです。
公平な対応に近づけるように
同じ相談窓口の看板を掲げているにもかかわらず、こっちの窓口の対応の評判と、こっちの窓口の対応の評判がまるで違うのは困りものです。
地域の住民さんにとってご自身で選べない窓口であればなお、不公平で不利益でしかありません。
評判のいい窓口に尋ねたいと思うのも、当然の心理です。
ただ、いくら専門職とはいえ、窓口に立つ人の対応や知識、力量に個人差があるのもまた否めません。
ニンゲンですもの、得手不得手も限界もあるでしょう。
私もあります(苦笑)
では、どうしましょうか?
地域の枠を超えて、担当エリアの枠を超えて、専門職同士、支援者同士、意識してつながることをお勧めします。
あなたが苦手とすることも、となりの同種窓口の担当者は得意分野かも知れません。
見栄やプライド、恥ずかしさは捨てるべきです。
あなたのためではありません。
相談者(利用者)のためです。
とは言え、いつかは、きっとあなたのためにもなります。
次にまた同じようなご相談があったとき、あなたは(たぶん!)もう一人でも対応ができるようになっています。
そのときは、ぜひ何食わぬ顔で悠々と対応しましょう(笑)
また、窓口の中には自分だけの一人職種(社会福祉士1人、保健師1人とか・・・)の窓口や、市内に一か所だけの窓口(市直営の地域包括支援センター)などもあるでしょう。
日々奮闘されているかとは思いますが、そのような窓口の方はかなり意識しなければ、それもって新たに支援の力量を向上させる機会が持ち辛いかも知れません。
自分以外の、または自分の所属する窓口以外の対応が、見聞きしづらい環境にありますからね。
もちろん、環境はあなたのせいではありません。
しかし、相談者(利用者)のせいでもありません。
それでも他所と同じ公平な支援や対応を提供することは変わらず求められます。
相談窓口が決められている住民さんのために、市町を飛び越えネットワークを構築し、他所の同窓口とつながることで、ご自身の支援の引き出しを増やしましょう。
あきらめ、または過度な自信は支援にとって有効ではありません。
誰かに教えを乞うてでも相談内容を解決してあげたいと思える支援者こそ、自己覚知と熱意があって、私は立派だと思います。
地域のために、住民さんのために、まずは窓口の支援者同士がつながりましょう。