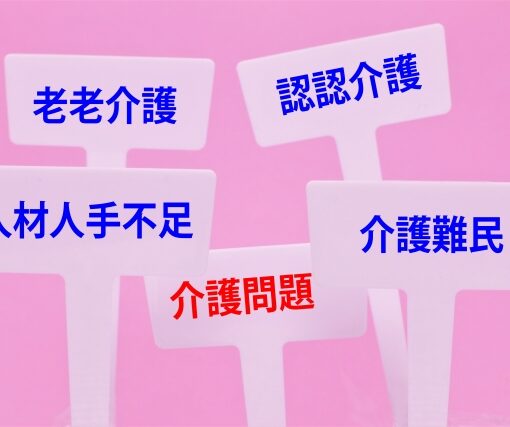*お読みくださる皆さまへ~ 以下のブログでは「ポストケアラー(支援)」について私自身の思うところや考えを述べています。しかしながら、当然ですが世の中には様々な視点や捉え方があります。また、それぞれに境遇があり、ときに自身ではどうしようもない厳しい状況にさらされている方もいらっしゃいます。今後、社会がどう変わっていくかもわかりません。そして、実は私自身も「ポストケアラー(支援)」についてはっきりとした考えがすべてまとまっているわけでもありません。まだまだ考え中であり、模索中です。「今」のこのときの自身の頭や心の中を整理するつもりで書いておりますので、どうかご承知おきください。
ポストケアラー支援を考える‐その①「喪失に寄り添う」
介護者支援活動の中で「ポストケアラー(実質的なケアを終えたケアラー)」のこと、またはその支援や支援の必要性が話題になることが増えてきました。
もちろん、厳密にはポストケアラーと一言に言っても、いわゆる看取り期を迎えケアを必要とされていた要介護者がお空に旅立ったあとのケアラーのこと・・・ばかりではありません。(のちほど解説しています。)
年齢も、性別も、さまざまです。
「誰が、誰のケアをしていたか?」ということでも、その内容は幾分違ってくるでしょう。
しかし、ポストケアラーについて考えるとき、まず共通して言えることは、ポストケアラー支援は「喪失のケア」であり、大切なひとを送ったあとのその人の「心に寄り添う支援」であると私は認識しています。
当事者ご自身が支援を必要とされるかどうかに個人差こそあれど、「心に寄り添う支援」という点においては、いわゆる老々介護のケアラーも、シングルケアラーも、若者・ヤングケアラーも、あらゆるケアラーが対象になるでしょう。
また、「ケアラー同士の集いの場の提供」「ケアにまつわる悩みや想いを吐露しあえる仲間づくり」を主たる活動とされている団体も多いケアラー支援団体の担う役割として、これからはさらにこの「喪失のケア」「心に寄り添う支援」も求められてくるかも知れません。
実際に全国各地の活動団体ですでに具体的な支援プログラムが動き出していたり、既存の活動の中に必要性を強く感じている話を耳にします。
*これまでの関連記事はこちら ↓ ↓ ↓
ポストケアラー支援を想う①~ケアラーのその後~ | オフィス紗代|毛利真紀|長崎県佐世保市の社会福祉士事務所 (nagasaki-officesayo.com)
ポストケアラー支援を想う②~ケアラーのその後~ | オフィス紗代|毛利真紀|長崎県佐世保市の社会福祉士事務所 (nagasaki-officesayo.com)
ポストケアラー支援を考える‐その②「ヤングケアラー、若者ケアラーが経験するケアのおわり」
先ほど、ポストケアラーは「要介護者の看取り期を終え、要介護者がお空に旅立った後のケアラー」ばかりではないと申し上げました。
ヤングケラー・若者ケアラーにおいては特に、いわゆる十代の頃から家族などのケアを担っている場合、ケアを必要とする状況そのものが終わったわけではないけれど、ある時点でケアを「主として担う人」が代わる場面も出てくることがあります。
家族などが介護を必要とする状況は変わらないけれど、担い手が代わるタイミングです。
例えば、ヤングケアラー・若者ケアラーが自身の生活環境を変えることで「ケア」から離れる。
ケアの状況が変わり、これまで担ってきた「直接的なケア」から自然に距離が生まれる。
これらは、もちろんヤングケアラー・若者ケアラーに限ったことでもなく、どの年代の、どの属性のケアラーにおいても言えることでもあります。
しかし、ご自身の年齢も若いヤングケアラー・若者ケアラーにおいては、年齢が若いゆえに起こりやすい状況かと思います。
ただ、とは言え、どのタイミングでケアから離れたり距離が生まれたとしても、彼らのそれまでの日々や人生において「ケアラーであったこと」は変わりません。
「ケアラーであった自分」を抱えながら、ときにはケアラーであったことで今やこれからにも影響を受けつつ、生きていくかも知れません。
そのような彼らの「拠り所」となり、何らかの支援体制が引き続きあることが望ましいのではないでしょうか。
若い彼らを「ヤングケアラー・若者ケアラー」にしたのは、多くの場合彼らの周囲にいるオトナなのですから。
ポストケアラー支援を考える‐その③「ケアラーになる準備はケアを終えたあとにもつながっている?」
「ケア(介護)」は生活であり、人生の中でつながっている。
「ケア(介護)」は誰にでも起こり得ること。
そう考えると、起こり得ることを「前もってイメージしておく」こと、「可能な限り事前に準備しておく」ことは、大切だと思います。
「仕事とケア(介護)の両立」においてあくまで労働の課題と考えれば、それは雇用主側だけではなく、労働者側においても、それぞれに心構えや対策(備え)が必要です。
ヤングケアラー・若者ケアラーなど若い年齢の方々はともかく、社会人として、一人の生活者として、少なからず一人ひとりに「自身がケアラーになること」を考える(考えておく)責任はあるのかも知れません。
自身の身近な大切な誰かが「ケアを必要とする状態になる」こと。
もちろん、実質的なケアを自身が主となって担うのか、はたまたサービスを使いこなしあえてケアから距離を置くのか、それもまたそれぞれの考えだとも思います。
選択肢をたくさん用意することも大切ですし、そうできればそれに越したことはないと思います。
大切なことはケア(介護)を「自分ごと」だと早い時期から認識して動き出しておくことです。
そうすることで、いざケアラー生活がはじまったときに、また「実質的なケアを終えたその後」もだいぶ違ってくるのではないでしょうか。
もちろん、備えておくことは「自分自身がケアを受ける状態になること」にも同じように言えると思います。
ポストケアラー支援を考える‐その④「ポスト(シングル)ケアラー支援と社会保障」
ポストケアラー支援が議論される時、話題にあがりやすいのが「社会保障」についてです。
特にこれまでケアを主として自身が担ってきた40代~50代のミドルシニア世代。
その中でも、シングルケアラーにおいては課題を多く抱えておられるように感じます。
たとえば「喪失のケア」以外にも「就労の課題」や「身元保証の課題」「経済的課題」など。
親などの要介護者を看取ったあとに、それまでのケアにまつわる支援者らが離れていき一人取り残される「孤独感・孤立感」なども傾向としてあるかも知れません。
確かに、課題は多いですね。
ただ、あくまで今現在における考えではありますが、私自身は、上記40代~50代のシングルケアラーがポストケアラーになった時の課題においては、それらをどこまで「行政課題」として捉え、「社会保障」を確立さえていくべきなのか悩ましくも感じるのが正直な気持ちです。
課題解決はもっと違う角度から、もっと手前の段階であるように思う。
「就労の課題」に介護離職等があるのであれば、「仕事と介護の両立」をどう整備していくのか。
ケアを担うために働けないことや介護費用が高額になることが「経済的課題」につながっていくとしたら、そもそもの「ケア(介護)」にまつわる介護サービス、障がい福祉サービスの仕組みが脆弱だからではないか。
「孤独感・孤立感」においては、私自身もシングルケアラーなのであえて申し上げますが、これまで「仕事」として関りがあった支援者らがその「仕事が終わる」と離れていくことは当然と言えば当然の形。
この状況における「孤独感・孤立感」は、どの属性のケアラーにおいても言えることです。
支援者らはあくまで契約上のサービスとして稼働しているわけですから、いつまでもそこに固執するわけにもいきません。
気持ちや想いだけの話ではない。
強いて言えば、そのあたりの役割として力を発揮するのが「ケアラー支援の活動団体」ではないでしょうか。
「ケア(介護)がはじまってから」「ポストケアラーになってから」ではない。
もっと手前の段階で、考え、取り組み、取りに行くことがあるように思う。
ケアラーであっても自分自身の人生であり、そしてはじまったケア(介護)は「いつか実質的には終わる」のですから。