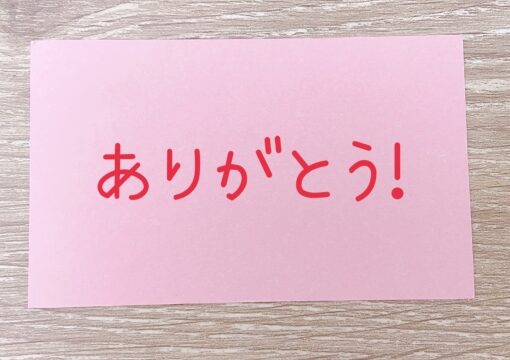福祉課題はピンポイントなもの?
「ケアラー支援」と聞くと今話題の?ヤングケアラー(子ども)のことだとか、はたまた介護保険(高齢者)のなにか~だとか、そう思われたり・・・
「行方不明に関する対策」と聞くと、認知症に対する課題だと思われたり・・・
しかし上記は、どちらも「障がい福祉」の課題にもある(はず)だと思います。
何かにつけて、やれダイバーシティだの、やれ多様性だのって言うでしょう。
そんな時代でしょう?
しかし、「ケアラー支援」や「行方不明に関する対策」と聞いても、すぐすぐ「障がい福祉の課題でもあるよね」なんてイメージはたぶん持たれない。
考えて取り組もうとしたら、イメージどおり?の子どもや高齢者福祉の窓口担当者や支援者らしか集まらない。
なぜでしょうね?
「障がい福祉」は児童福祉・高齢者福祉のそのあとになりがち
支援も、そんなピンポイントな時代ではもはやありません。
これまでも実はそうではなかったということに、担当窓口や支援者らは早く気付いた方がいいです。
だからなのかはわかりませんが、日本の障がい福祉(対策)は何かにつけて遅れます。
高齢者や子どもとは、一緒に進まないことが多いです。
残念ながら、取り組まれるのはだいたいいつもそのあと。
「多機関型相談窓口」の設置という取り組みも増えてきてますよね。
しかし、オールマイティな相談窓口の設置が騒がれますが、イマイチ・・・
そうそううまく初めから軌道に乗ってるようにも見えません。
作った側が、そういうところ作って満足!している感が、正直私は否めません。
長崎県内でも、現場はまだまだ課題多しだとお見受けします。
もちろん、その発想や取り組みはありがたいですけどね。
専門家がつながっておくこと
設置された相談窓口が一緒だろうが、別だろうが、各々の専門家がちゃんと繋がって、そしてずっと「繋がり続けておくこと」の方が大事ではないかと思います。
自身にない専門性を必要に応じてお互いに貸したり借りたりすることが、大事だと思います。
専門家として繋がっておきさえすれば、むりくり専門外の他分野のことをさほど勉強せずともすみます(笑)
いいじゃないですか。
知らないものは知らないし、そもそも専門家って何かに特化しているから専門家なのです。
餅は餅屋・・・
その道のプロにはかないませんしね。
なにより、課題を多角的に捉えようとすることは、今やこれからのいかなる支援においても必須です。
そのためには多角的な視点が必要で、十分な知識も必要です。
何某に特化していたところで、あくまでその一部の専門性が高いだけでそれは多角ではないと思います。
課題解決には、まず「多角的視点が集まっていること」が大切なのです。
課題はいつも「生活の中」にあり繋がっているから
誰もが、毎日、自分の日常を送っています。
人それぞれに状況は違えど、その生活は人々にとってなにも特別なものではありません。
そして、課題はいつも生活の中にあって、それぞれがどこかで繋がっているものだと思います。
個人の中で、家庭の中で、地域の中でつながっています。
そうであるならばなおさら、担当窓口も支援者もつながりましょう。
もちろん多機関型相談窓口もいいのです。
しかし、つながった専門家集団も、各々の所属先が違うだけで、繋がってさえいればそれはそれで実用的でかつなかなか「強く頼もしいもの」だと思います。
高齢化、病気、障がい、労働、子育てや教育、地域・・・
専門家たちが何かと課題提起しがちなそれらも、全部、人々の生活の中にあり、そして繋がっているのですから。