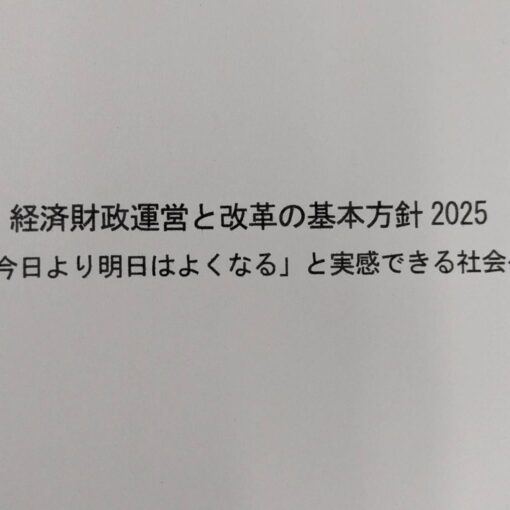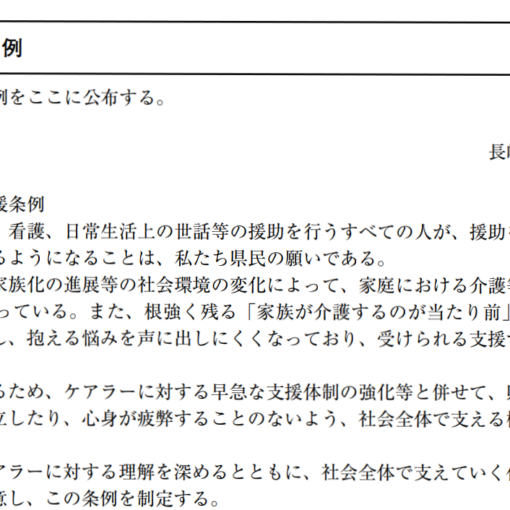ケアマネジャーさん、ソーシャルワーカーさんへ~ケアラー支援においても、皆さんのアセスメント力が試されます~
専門職がケアラー支援に向き合うとき、特に、仕事を辞めて介護に専念している状況を抱えるケアラーに対して、支援者(ソーシャルワーカーやケアマネジャーなど)にありがちだなと思うこと。
それは、「離職した(仕事を辞めた)」こと自体を、すぐにそのケアラーの「課題」だと決めてしまいがちなところです。
話を聴く以前に、事実を確認する以前に、頭っから決めてしまいがち。
専門職であれば、
1:その背景に何があったのか
2:どんな想いがあったのか
3:実は「介護以外に」何かあるのか
4:どうしてこの状況になっているのか
深くアセスメントして、その目の前の事象だけに目を向けるのではなく、もっと奥深い部分にも視点を置く必要があると私は思います。
ケアマネジャーさん、ソーシャルワーカーさんへ~その価値観は、誰の価値観ですか~
私たち相談支援の専門職は、自分自身でとても強く意識して気を付けないと、ある事実を自分の思う方向性に持っていきたがる傾向にあるのではないか・・・
支援とか、援助とか言いながら。
仕事を辞める決断をすること。
そして、介護に専念することが、あたかも「悪」のように捉えているその価値観は誰の価値観ですか?
もしや他に何か理由があるのではないか、とは思いませんか?
単純なことで「生計の立て方」にしても、その人、その家族(家庭)、それぞれのスタイルがあっていいはずだと私は思います。
ケアマネジャーさん、ソーシャルワーカーさんへ~長崎県ケアラー支援条例制定を目前にして~
専門職のいわゆる一方的な「正義感」や「義務感」が実は当事者を追い詰めていることだってありうる。
・・・かも知れません。
支援者が、ニンゲンに目を向けずに事象にばかり気をとられると、上記のようになりがちではないか・・・と、これまでの自責の念も含めて思うのです。
長崎県ケアラー支援条例が、予定ではまもなく、県議会において「可決」されます。
今、全国的にケアラー支援に追い風が吹いている。・・・と、言われています。
それは、とてもありがたいことです。
当事者としても、求めていた世の中の動きです。
行政やご尽力いただいている議員の皆さまには、とても感謝しています。
とはいえ、我々には専門職としての捉え方があって、冷静にやるべきことがあります。
我々の専門性とはなんでしょうか。
世の中の動きがどうであれ、我々自身が忘れてはいけないのではないかと思います。