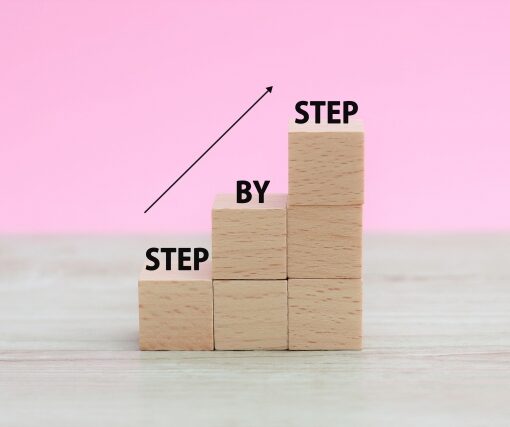「福祉職」と聞いてどんなイメージがありますか
何かに対する印象やイメージの持ち方、持たれ方は、もちろん個人差があるとは思います。
「福祉」や「福祉職」に対してもそうです。
良いイメージもあれば、そうでないイメージもあるでしょう。
今回は、そんな「福祉職」に対する印象やイメージの中でも、世間の人からみたイメージではなく、自身が福祉を生業にしているひと、福祉業界における内輪のお話。
「掲げる理想像」と、されど「現実」のお話です。
福祉職だって「生身のニンゲン」ですから・・・
私は、「福祉」を生業にしている者にもときに「息継ぎ」と「休息」が必要だと思っています。
「愚痴」しかり。
ときに、「ご褒美」しかり。
専門職としてのプロ意識を強く持つことは大事です。
でも、いつもそれだけで突き進むのも難しい。
それは、福祉職とはいえ、ひとりの生身のニンゲンだから。
そうそういつも、自分で自分のメンタルを穏やかに保てるものでもない。
そう考えています。
誰しもひとりの感情のあるニンゲンだから。
自分自身にも同業者の仲間に対しても、まずその点における理解は丁寧になされた方がいいと思っています。
福祉の「専門職」として大事なこと
とは言え、私はそもそも福祉に限らず「専門職」という人に対して求めるものが厳しいことは自覚しています。
それは、自分自身に対してもそうです。
しかし、その自覚はあるけれど、なにも「弱音も本音も吐かずに、常に歯を食いしばって頑張れ」などとは言っていません。
きちんとプロとして仕事すること。
されど、ときにモヤっと「本音」が出てしまうことはどちらも大事。
今が「何のための」時間で、今の自分の「ポジション」はどこなのか。
今は「プロとして動くべき時間」なのか。
もしくは「本音でモヤモヤしていい時間」なのか。
きちんと「自覚」と「区別」があればいいと考えます。
そして、そのメリハリの必要性を一番理解しあえるのはやはり「同業者」だと思う。
「同業者」だからこそわかり合える感覚がある
仲間が、
「〇〇ですごくしんどかったけれど、その場ではどうにか頑張ってきた・・・。」
と話すのを聞けば、その頑張りと、よくグッとこらえてその場、その時間をやり切ってきたプロ意識を存分に称えたい。
「そんな愚痴や弱音なんて言わないのが福祉のプロだ!」
なんてご意見もたまに聞こえてきますが・・・・
本当にそうでしょうか。
プロフェッショナルという職業の人が、24時間、なんどきもその何某のプロかと言えば、実際はそうでもないでしょう。
一旦、プロのスイッチが入ったら、「その時間は」プロの職業人として頑張るのがプロフェッショナルではないですか。
プロである前に、ひとりのニンゲンとしてのその人があるはずです。
福祉職だってそうです。
そして、一人のニンゲンとしての「しんどさ」を抱えながら頑張ったことを一番に理解できるのもその同業者。
同業者だからこそ理解しあえる「感覚」を共有することで、報われる苦労があると思います。
我々の「支援」は、多くがひとりで進められるものではありません。
支援者らもお互いに、プロとしての実力も、されど心の内側に持つ本音や弱音も、どちらも共有することでより強い支援チームになれるのではないでしょうか。