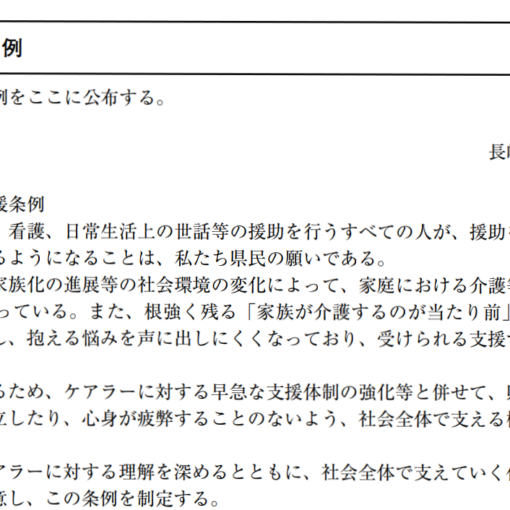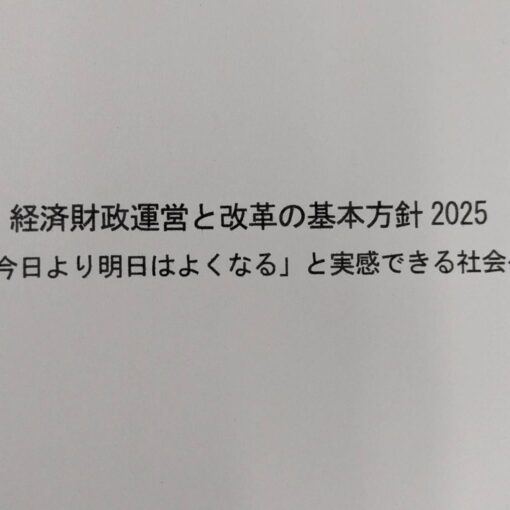「仕事と介護の両立支援」は社会的課題のひとつに
昨今、労働者「不足」や労働者の「離職」がさまざまな分野において課題になっていることは、メディア等でも日々報道されているとおりです。
ケアラーを取り巻く状況においても、働きながら家族等のケア(介護)を担う「仕事と介護の両立」や、介護を理由に仕事を辞める「介護離職」などが、社会的課題として取り上げられるようになりました。
もちろん、国の政策においてはまだまだ課題は山積みでこれからですが、政府の取り組みとして動き出していることは大きな一歩だと感じています。
働くケアラーの「労働環境」もようやく変化のときを迎えたのかも知れません。
仕事と介護の両立支援や介護離職防止への取り組みが進むことへの期待
私は、過去に介護を理由に仕事を辞めたことがあります。
他に選択肢を考える余裕もなく、突発的に勢いで介護離職してしまいました。
また復職したあとも、仕事と介護の両立において自分なりに四苦八苦してきました。
そもそも自分自身に今ほどの仕事と介護の両立に対する考えや情報もなかったこと。
また、当時はそこまで仕事と介護の両立(支援)が「社会的課題」としても取り上げられていなかったことも原因かも知れません。
自身にそのような過去があるのでなおさら、少しずつとはいえ国をあげて「仕事と介護の両立」や「介護離職」について課題提起され、体制整備に向けて取り組まれようとしていることはひとりのケアラーとしても素直に嬉しく思い、今後の動きにも期待を寄せています。
たとえ、ことの発端に「労働者不足」の課題があったとしても、私はそれもまた現実だと思う。
仕事と介護の両立(支援)は【労働の課題】である
私はケアラー当事者であり、「ケアラー支援」の活動家です。
ケアラーが陥りがちな「孤独感」や「わからないが故の混乱」も身をもって経験しています。
そのようなケアラーが減ることを祈って、活動を続けています。
しかし、先述のとおり、先般の「仕事と介護の両立」や「介護離職」の課題に対する国としての取り組みや視点の置き方に、あらゆる分野で起こっているまた今後さらに広がることが懸念される「労働者不足」の課題が大きく影響していることは理解しています。
団塊の世代が75歳以上になるときを目前にし、そのジュニア世代が50代前半のときが迫っています。
このまま国として本気で対策を取らなければ、過去の私のように、突然始まった介護に慌てた働くケアラーが突発的に退職し、途方に暮れる・・・だけではなく、国はますます「労働者不足に発車がかかる」わけです。
もちろん、当然国としてもこの見解はあって、だからこそ対策に動き出している。
誰かのケア状況を抱えた「一人のケアラーでもある労働者」が自身の「就労」を継続するために取り組み、なおかつそのサポートを企業や国も一緒にやろうとしていること。
そう考えるとなおさら、仕事と介護の両立や介護離職への取り組みは「労働の課題」であり、いわゆる従来の「ケアラー支援」とは違うと私は考えます。
仕事と介護の両立支援における重要なこと
ケアラー支援の活動をしていると、ときどき介護が始まったばかりの頃の私と同じように「勢いで」介護離職したケアラーさんとの出会いがあります。
その後の試行錯誤の末、介護環境がある程度整い、「ケアの部分においては」生活のリズムがつかめてきます。
ケアに関しては一区切りつくのですが、しかしながらケアラーさんがいつまでも復職される様子が見受けられないこともあります。
なんらかのモヤモヤがあって、次に進めない。
このようなケアラーさんに対して、私は「まだ」仕事と介護の両立への働きかけは難しいと感じます。
むしろ、今すべきアプローチはそこではない。
なぜなら、ケアラーさん自身に「働く気持ち」がないから。
仕事と介護の両立において、まず重要なのは働くケアラー自身の「労働者としての働く意志」です。
ケアラー支援と仕事と介護の両立支援は一括りにはいかない
介護環境が整い日常のケアに概ね見通しが立ったとしても、日常生活の中で「ケア」と「仕事」のバランスをとることまではご自身の気持ちが持っていけていない。
まだ不安があり、なんらかのモヤモヤを抱えている。
むしろ、そのモヤモヤは「仕事」のことではないとしたら・・・
このような心理状態のケアラーさんに対して、「仕事と介護の両立」をどんなに説いてもおそらく響かないでしょう。
仕事と介護の両立に取り組んでいく主体はあくまで「労働者であるケアラー自身」です。
そして、仕事と介護の両立、強いては不本意な介護離職を防ぐために体制整備を行い働くケアラーである従業員をサポートするのが「企業側(雇用主側)」です。
働くケアラーが自分自身で「一人の労働者としてどう働いていくか」という意識を持てないうちは、どんなに仕事と介護の両立のためのサポート体制があってもおそらく使いこなせないし、まず使いこなそうとしません。
まずは、ケアラーが抱えるモヤモヤは何なのか、何がモヤモヤさせているのか、そこに支援が必要です。
そして、その支援は仕事と介護の両立支援ではなく、モヤモヤを晴らしケアラー生活を前向きなものにできるようサポートする「ケアラー支援」でしょう。
仕事と介護の両立のための体制整備は、今、そして今後の「労働力の確保のため」であることは間違っていないと思います。
だから、仕事と介護の両立は【労働の課題】なのです。
ただ、それを周知徹底し進めていくためには、まず労働者である従業員がもし働くケアラーになっても「働こう」という意志を持ち、仕事と介護を両立させる気持ちでいなければ成り立ちません。
目の前のケアラーが何に悩んでいて、どのようなモヤモヤを抱えているのか丁寧にアセスメントされて、今のその人に必要なサポートが届けられることが大切ではないでしょうか。