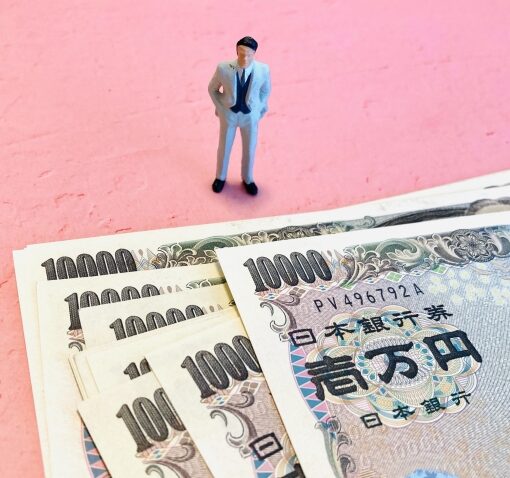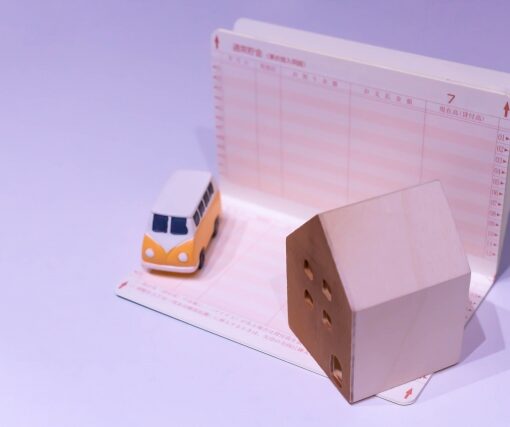社会福祉士としての自分自身の「可能性」を振り返る人が増えてきた?
コロナ禍の影響もあり、昨今、多くの方々の働き方が多様化してきています。
働き方と同様に、生活スタイルそのものを見直した方も少なくないかも知れません。
そのような影響もあってか、組織に所属する社会福祉士の方々からも、ご自身の「働き方」についてご相談を受けることが増えてきました。
福祉・医療の支援現場も、ここ2~3年で大きく変化しています。
コロナ禍により見直したこともあれば、やむを得ず変わったこともあります。
特に「相談支援」や「つなぐ」ことを生業とする社会福祉士にとって、コロナ禍における支援現場の変化は、クライエントさんへの関わり方、そして相談支援援助職としての自分自身の可能性を考えさせられることも多かったのかも知れません。
働き方のスタイルは見つけたけれど・・・・
支援現場や所属組織が変化してきていることから、ご相談の中には、自身が専門職として「組織に所属すること」自体を振り返る方も増えている印象があります。
独立した形での働き方に、専門職としてのご自身の可能性をより見出すような。
それもまた一つの選択肢であると思います。
私自身もそうして、自分の働き方を変えてきたひとりです。
ただ、ここで多くの方が立ち止まってつぶやかれるのが、
「自分だけで、本当にやっていけるだろうか。」
理想とする働き方のスタイルが見つかり、そのための準備をいろいろと進めていかれる中で、この「自分だけで、本当にやっていけるだろうか。」という漠然とした不安は多くの方にありがちです。
足りないものは、たぶん誰にでもある。
人の能力や可能性に対して、他人がとやかく言うのはあまりよろしくないかも知れませんね。
ただ、私自身も所属組織を退職し、数としてはそうそう前例も多くはない中で、独立起業を目指し切磋琢磨してきた一人ですので、その点においてはこれから独立起業を目指す後輩の皆さまへひとこと申し上げたいと思います。
「そもそも、誰しも完璧なわけがありません。」
我々は「専門職」といわれる職業です。
何某の「専門性」を生業としています。
しかし、逆を言えば、その何某以外のことに「専門性」なんて往々にして持ち合わせていません。
もちろん、いくつかの専門性や実績を兼ね備えている方もいらっしゃいますが、多くはそうでもないのが現状だと思います。
ただ、多くの場合、専門職とはそういうものです。
そう考えると、足りないものなんてたぶん誰にでもあって、足りないものを補ってからはじめようとされるならば、いつまでたってもスタートは切れないのではないかと私は思います。
やっぱりこれ!「自己覚知」と「ネットワークの構築」
社会福祉士が独立起業する上で絶対的に大事だと思うこと。
それは、自分自身の得手不得手を自覚し、それを補う努力をし、かつ補うために必要な手段を「自分自身の努力以外」にも持っておくこと。
自分には何が足りないのかを、自分自身で知っておくことは大切です。
その自覚がないと、足りないことを学んだり、得ようとする努力につながりません。
そして、さらに大事なことは、自分の不得手なことを「専門」とする方とつながっておくこと。
ネットワークを築いておくこと。
そもそも、何でもひとりで抱え込むのはプロではないと私は思っています。
クライエントに対し「自分が、自分だけが、解決に導いてあげられる。」という思い込みは、ワーカー自身の自己満足に過ぎません。
場合によっては、そのワーカーの思い込みがクライエントにとって不利益を生みかねません。
自身の働き方として組織に所属していても、独立していても、クライエントや課題への多角的視点とアプローチが有益であることは変わらないと思います。
そうであるならば、独立起業=「ひとり仕事になる」のではなく、「独立してからの他支援者らとのつながり」をどう構築していくかを考えることに重きを置いた方がいい。
独立起業し、うまくやってそうに見える人っていますよね。
「勉強し知識を深める」などその方ご自身の努力ももちろんですが、その方のプロとしてのもっと深い部分に目を向けてみた方が、いろいろなヒントが得られるかも知れません。
案外、その方お一人ではなく、もっと広い視点でたくさんのネットワークの中で動かれていることに気づかれるのではないでしょうか。