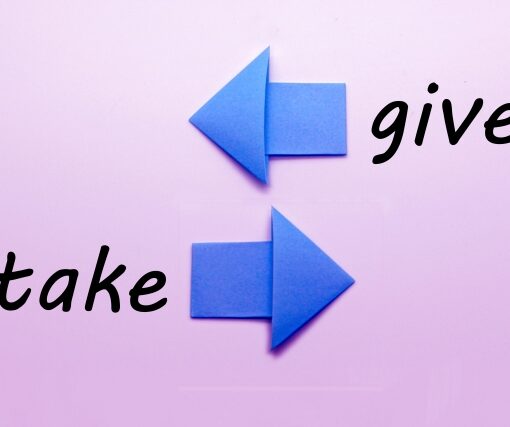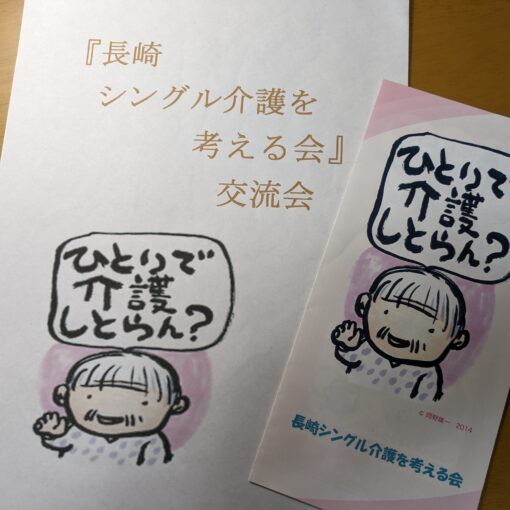「家族介護者向け介護(技術)教室」の開催の目的はなんですか?
行政主催でありがちな「家族介護者向け介護(技術)教室」を、市町行政が「ケアラー支援の取り組み」として認識されているとしたら、それは違うと私は思います。
少なくとも、それで「我が市(町)は、ケアラー支援に取り組んでいる。」など、満足して欲しくもありません。
ケアラーを、結局のところガッツリ!「介護の担い手」として捉えられているような・・・・
そんな印象が否めません。
そもそも「ケアラー支援」を考えるとき、もうそれら催しや取り組みを「ケアラー支援」と呼ぶような、そんな時代ではないのです。
参加する「目的」も、本当に明確なものですか?
行政の「家族介護者向け介護(技術)教室」は、開催してもいい。
だけど、「ケアラー支援」ではない。
私はそう思います。
もちろん、そんな教室無意味だとか、なにもそんなことは言っていません。
介護技術を学びたいケアラーさんは、学ぶこと自体はいいと思います。
しかし、それが「ケアラー支援」かと言えばそうではないだけです。
ケアラー自身も、自分の意志とは無関係にその技術を身に着け家族介護に携わることが当然という空気感の中で参加しているのであれば、それは「強制的」であり暗黙の「強要」だということを、きちんと認識された方がいいと思います。
もちろん実際には、要介護者に指1本触れずに一緒にいられるかと言えば、そういうことでもないかも知れません。
いずれにしても、いろんな意味でケアラーにも「自覚」は大事かなと思います。
考えもあって、されど実情を理解し納得して行動するのと、ただただそういうものだと思いながら「やらされる」のはだいぶ違いますよね。
「家族介護力の維持」から「介護者の人生の支援」へ
家族が、必ずしも「介護の担い手」であるという前提はもはや時代遅れです。
それを裏付けるものに、平成30年(2018年)3月に、厚生労働省から発行された下記のマニュアルがあります。
市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル(厚労省)
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/00085.html
このマニュアルの中で、厚生労働省は、これまでの「家族介護者支援」目標があくまで「家族介護力の維持」であったことを改め、今後は「介護者の人生の支援」であると明記しています。
さらに、これまでの支援対象者が「要介護者(介護を必要としている本人)」のみであったことについても、今後は要介護者と同じように「家族介護者(ケアラー)」も主たる支援対象者とみなすことも書かれてあるのです。
そう考えると、これまでの家族介護者支援において、介護者に対する「介護ノウハウの習得支援」がいわゆる「家族介護者向け介護(技術)教室」の開催であったわけですね。
少なからず当時の考え方や方向性としては、それでも通っていた(通していた?)。
しかし、今は、厚生労働省が示す「介護者支援」の考え方や目的からも、「家族介護者向け介護(技術)教室」の開催を、市町のケアラー支援の取り組みに位置付けることは間違っていると捉えることができます。
今後の市町行政のケアラー支援への取り組みに影響しかねない
私はなにも「0か100か」とか、そういう風に極端なことを言っているつもりもありません。
何度も申しますが、介護技術を身に着けたいという意思や目的がご自身ではっきりしているケアラーさんは、学ばれて結構だと思います。
また、そのような教室が開催されることを真っ向から否定もしていません。
ただ、ケアラー支援条例制定やその前後の動きも少しずつ進められている昨今。
今後、市町行政のケアラー支援において、「家族介護者向け介護(技術)教室の開催」がケアラー支援の取り組みとして市町に認識されたり、取り組みを達成しているかのような勘違いが生まれかねない。
もはや考え方として時代に逆行している。
それが心配なのです。
厚労省は、平成30年(2018年)3月に先のマニュアルを発行しています。
もう、それからすでに数年が経過しています。
そろそろこのあたりで、視点や価値観がきちんと切り替えられることを願います。