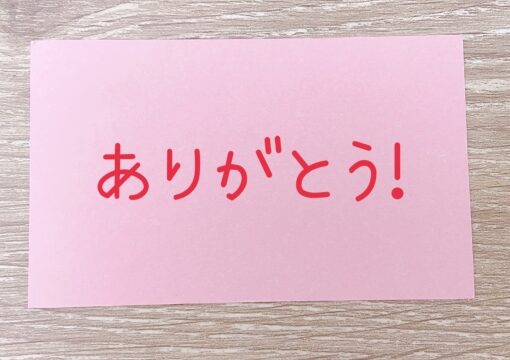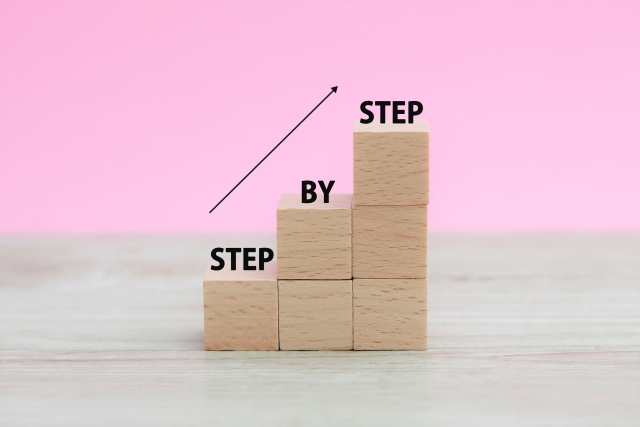
私の日頃の業務は、家事や民事の内容がほとんどなので、刑事事件に携わることはほぼありません。
まあ、自身がそんな風なので、たぶん言えることでもあるのですが・・・
最近、リーガルソーシャルワーク研修のご案内で、内容的にいわゆる「更生保護」とか、そういうプログラムを多くお見受けします。
司法も福祉もひとの「生活」「人生」の話なので、もうちょっと「更生保護」のピンポイントさではない、司法と福祉の連携に関する学びの研修があると嬉しいなと、個人的には懇願しています。
当然、お互い異業種ですし持ってるものも違いますが、仕事の先にひとの「生活」や「人生」があるということは共通していますよね。
だからこそ。
以前は、更生保護に限らず、司法と福祉の連携や課題の捉え方を学ぶことがメインの勉強会や、双方専門職としての出会いの場を頂ける機会もちょこちょこありました。
今現在も、日頃の業務でなにかと法律のからむ課題を抱えたときや判断に迷ったときにご指導いただくのも、この頃出会った弁護士さんや司法書士さんがほとんどです。
ありがたいことだなと感謝しております。
司法事務所に飛び込みで入るって、さすがに緊張しますよね(笑)
しかし、ここ数年は、このような勉強会や出会いの機会がコロナ云々でめっきり減ってしまいました。
残念です。
じゃあ、自分に何ができるのか・・・
ないなら、どうするのか。
先立つものはどうするのか。
模索中~です。
もちろん、司法機関にソーシャルワーカーの配置が進んでいますし、携わるソーシャルワーカーに司法領域の基礎的な知識の習得が必須なのは理解しています。
司法機関に入っていこうとしているのはソーシャルワーカー側ですしね。
法律家がどう感じてるかはともかく、「入っていきなさい!」というのが国の方針でもあるのでしょう。
ただ・・・
だいぶ以前の話。
結果、踏み倒す(←言い方・・・)すべのない支払わなきゃいけない債務を、なぜ支払わなきゃいけないのかという部分について弁護士さんに解説してもらって、それを同行した私が85歳のおじいちゃんにかみ砕いて伝える・・・
ということをしたことがあります。
専門家も考え方はいろいろなので、弁護士さんと私のこの動きに対し賛否両論あるでしょう。
弁護士さんにも、私にも。
でも、私はこのときの弁護士さんとは、僭越ながら「お互いに、お互いの立場から、やるべきことをやった。」と思っています。
そして、こういうことを、これからも丁寧にやっていきたい。
自分で、時効援用通知を上手に作れるようになりたいとか、なにもそんなことではない。
それを作るのが私の仕事ではない。
ただ、その「仕組み」を自分がきちんと理解した上で、クライエントさんに丁寧にお伝えしたいのです。
自分の担当する事案に正しく落とし込みたいのです。
福祉職としての自分に課せられた、大事な役割だと思っています。