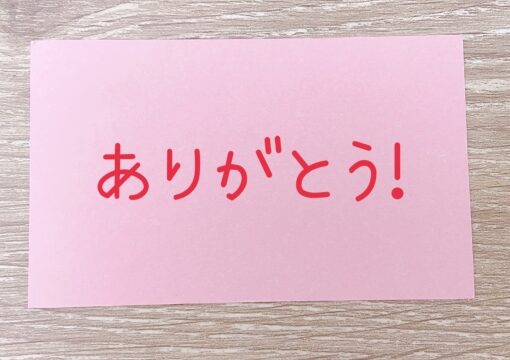行政機関の中の社会福祉士はまだまだ少ない。
市町行政機関(市役所や町役場など)の中に社会福祉士が雇用されることと、その専門職としての組織に対する責務・・・なんてことを、後見の実務を担い市町の利用促進体制整備にもちょっとばかし口を出すようになって、より深く考えるようになりました。
想えば、自身が「もっとしっかり勉強しなければ・・・」と、自分自身に対して意識しはじめたときも行政機関に勤務しているころでした。
社会福祉士は、残念ながらまだまだすべての市町行政機関に完全に雇用されるまでありません。
雇用されていても(自身もそうでしたが)臨時職員だったり、非正規枠の採用も珍しくありません。
もちろん、自治体にもよるところですが、その数はまだまだ少ないのが現状です。
命、それから生活の「質」
なぜ、市町行政機関に社会福祉士の雇用がまだまだ少ないのか。
これはあくまで私の持論ですが、ざっくり言えば、一番真っ先に大切なのは「命」のことだから。
「福祉」は、あくまで生活や人生の「質」の部分。
もちろんどちらも大事ですし、権利も人権も考えられて然るべきですので、それは本来比べることはできないものかも知れません。
しかし、命や病気や赤ちゃんの出生、そして子育て。
どうしてもそちらに重きが置かれます。
それもまた、当然かも知れませんね。
であるからして、市町行政機関に保健師などの医療(保険)の専門職が正規雇用で配置されていて、しかもかなりの人数が雇用されていて、されど、社会福祉士がその割合からしてどれだけ少ないか・・・たぶん、半分の数もいないと思います。
市町行政に限ったことではありませんが、いわゆる「専門職」を雇用するということはいろいろと工面が必要です。
雇用する側としては、財政的な課題も当然出てくるでしょう。
そうなったときに、どうしても「福祉職」は「医療職」の後になってしまうのが実情ではないかと思います。
庁舎内において専門性を発揮すること
しかし、とは言え市町行政において、少しずつですが社会福祉士の正規雇用や非正規であってもその数は増えつつあるのも現状です。
私の周囲でも、以前は非正規の社会福祉士しか配置されていなかった行政機関で、正規雇用の社会福祉士が配置されているのを見かけるようになってきました。
我々の専門性を必要とされているということは、住民さんたちの生活の質や権利についてより高い専門性をもって変えていこうとされているのだろうと感じ、嬉しく思います。
そうであるならば、我々もその期待にもぜひ応えていかなければいけませんね。
ここで、前述した「行政内における専門職としての組織に対する責務」について、日頃感じていることをお話したいと思います。
私は、いかなる専門職であっても、行政機関に所属する者であるならば特に、その地域の住民さんたちに対してその専門性が発揮されることは当然だと考えます。
そのために雇用されているのですから、それは何も特別なことではありません。
それは当然の働きとして、重要なことは所属するその行政機関内においても専門性を発揮することではないでしょうか。
それは、地域住民さんの利益につながります。
最近は、多くの市町で成年後見制度の首長申立が増えています。
と言うことは、市町行政機関内に成年後見制度の「利用支援」の対応をする職員がいるということであり、社会福祉士が担っていることもめずらしくありません。
もちろん成年後見制度の利用支援が社会福祉士の業務のすべてではありません。
しかし、成年後見制度があくまで「権利擁護」のための制度であることを考えると、担当する専門職としてはその「権利擁護を生業とする」社会福祉士が多いかと思いますし、適任と考えて頂くのが自然ではないでしょうか。
社会福祉士の専門性にきちんと着目し、成年後見制度利用支援の担当者に社会福祉士を配置されている市町行政は頼もしいと思います。
配置された社会福祉士にはぜひ力を発揮して頂きたいですし、何度も言いますが地域住民さんたちの福祉の向上に努めて頂きたいです。
そして合わせて大事なのは、権利擁護を担当する部署内に限らず、その行政機関内においても専門性を発揮すること。
成年後見制度を利用するにあたり、今後利用者の生活はどう変わっていくのか、何が守られ整理されていき、環境はどう整えられていくのか、これからの見立てを庁舎内を含む関係者らにきちんと説明できることも重要な任務だと思います。
そのような働きかけを通して、成年後見制度を利用する意味や仕組みも伝わっていくはずです。
市町の福祉や権利擁護への認識は全体的に変わっていくはずです。
市町行政機関に所属する社会福祉士の重要な任務の一つだと私は思います。
そして、庁舎内の福祉(権利擁護)に対する認識の変化は、必ず地域住民さんの利益につながっていくと思うのです。