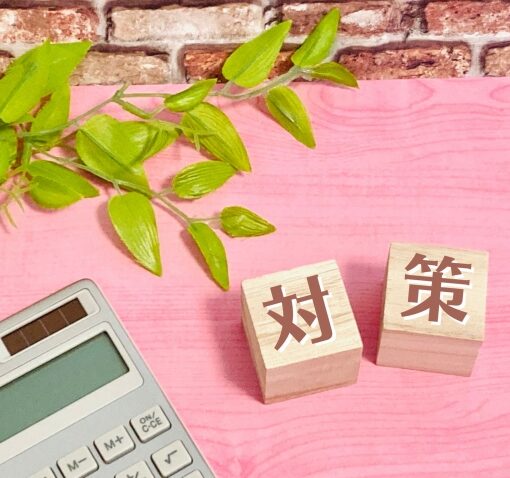「独立起業」のご相談~最近は「働き方」も選択肢がいろいろ~
独立起業して4年目になります。
社会福祉士の方から、今もときどき独立起業についてご相談を受けることがあります。
このブログでこれまでにもそのテーマでさんざん書いてきましたので、おかげさまであまりトンチンカンなご質問は受けなくはなりました。
しかし、最近は、我々社会福祉士もいろいろな働き方や、そう考えることが出来るようになってきたのだろうとつくづく思います。
これまで道を切り開いてきてくださった諸先輩方に感謝ですね。
ただ、ご相談を受ける中で、「ん・・・。大丈夫かな?」と、生意気にも感じてしまうことも最近増えてきているように思います。
私は40代で起業しました。
肌感触ではありますが、最近は、私の周囲でももっと若い年齢で起業を考える方も増えてきているようです。
このブログでも公表しておりますが、私は30代~40代はじめにかけて、どっぷりケアラー生活を送っておりました。
なかなか自分自身の働き方を立ち返り考えるまでにも時間がかかったので、若い皆さんにはただただ「すごいなぁ」と思ったりしています。
もちろん、何も年齢だけがどうのこうのと言っているわけではありません。
気になるのは、ご自身の「印象」について。
どうお考えなのか見えないことです。
責任のある仕事を「任せたいと思ってもらえる自分」であり続けること
社会福祉士が独立起業するにあたり、「後見業務の受任」で身を立てていこうと考えているご相談もまた多いです。
お考えは、なんとなくわかります。
実際のところイメージしやすいですし、そのためのルートもはっきりしています。
しかし、おそらく、「どうすれば受任できるようになるか」、ただそれだけですといつかどこかで何らかの形で壁にぶつかる気がします。
そして、当たり前ですがあくまで仕事です。
ビジネスプランも必要だと思います。
当然、収入のことも然り。
後見業務の実務は、その数字的な部分がある程度見込みがたちますし、その点においてはわかりやすくはあるかも知れません。
ただ、やるのは自分なんですよね。
社会福祉士会という組織に所属するとはいえ、個人で受任するのであれば、後見業務は往々にして自己責任であることが多いです。
念頭に置かなければいけない課題はそこにあると思います。
実務において行動や判断、何にしろ自分自身で責任をとるわけです。
そんな責任の重い仕事を「任せて頂ける自分」であり続けること。
任せたいと思って頂けるかどうか、そうあり続けられるかということに、実はかなりのエネルギーと意識が必要だと思います。
ご自身のその「印象」に腹くくれてますか?
福祉職とはいえ、いや、福祉職だからこそ経営者(起業家)としての自身の見せ方、いわゆる外に向けたプロモーションが大事にもなってくるかと思います。
印象とか、イメージとか、それがあっての現実の自分とか。
そのバランスは大事です。
ときには印象と現実のギャップなんかも、その効果のほどを計算の上であれば私はそれもまたいいと思います。
全部ひっくるめて自分自身で責任を持ち、なおかつコントロールできていること。
独立起業していくうえで、そんなことも実は大事だったりするのではないかと思うわけです。
つまり、後見業務しかり、独立起業するということは自分で「仕事をとっていく」わけですから、「任せて頂ける自分」を自分自身で表現できなければ、誰もそれを代わりにやってくれる人はいません。
それは自分でやるしかないし、自分でしかできないのです。
世の中いろいろな方がいますし、いろいろな価値観の方がいます。
必ずしも自分自身とぴったり波長や考えが合う方ばかりでは当然ありません。
一方では評価され、しかし、同じ自分なのに別のところでは完全に批判されることもあります。
そういったことに対しても自分で納得し、きちんと理解し、そのうえで「私はこういう者だ」と表現していくことが大事だと思います。
自身の表現が必ずしも「プラス」に働かないかも知れないことに対する覚悟。
そこがゆるいと、ただ「甘んじているひと」になってしまうかも知れません。
独立して「仕事をとる」こと。
それはただそのルートに乗っかるとか、実務における技術的なことだけではなく、「仕事を任せて頂ける自分」であり、また「その自分をどう表現するか」も重要ではないでしょうか。