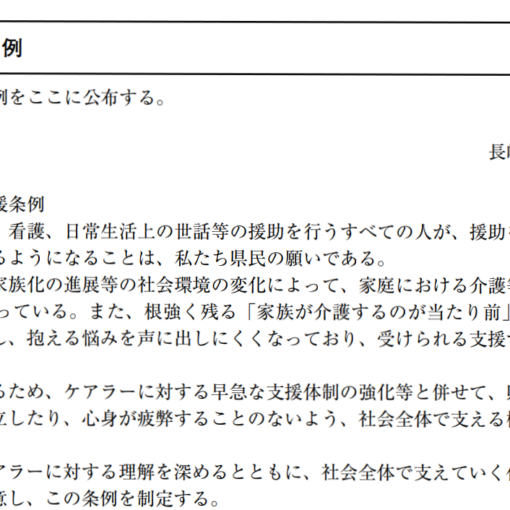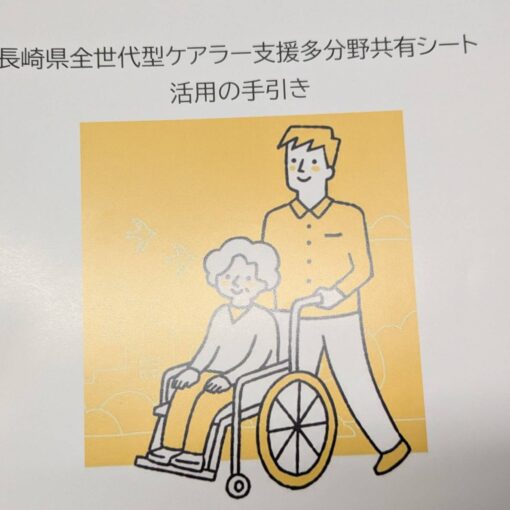ケアラー支援への意識が変わっている
昨今、「ケアラー支援条例」制定への動きが、新聞やネットニュースなどメディアでも取り上げられています。
そして、それは単に関東など都市部だけの動きではありません。
その進み具合に違いはあれど、地方でも同じく進められようとしていることです。
ですから、「とは言え、このあたりみたいな田舎は・・・」なんて、決して思わないでください。
私自身の親の介護がはじまった十数年前もケアラー支援の活動はもちろんありましたし、その必要性に声を上げてくださる支援者の方々もいました。
ただ、今日のように、国をあげて・・・というほどまではなかったように記憶しています。
それだけ、我が国においてケアラー(=家族介護者)の存在はある意味当たり前であり、特別なものではなかったのかも知れません。
注目されているヤングケアラー
先日、自民・公明・国民民主3党が、「ヤングケアラー支援」をめぐり法制化を検討する方向で一致したという記事が出ていました。
厚生労働省のホームページにあるヤングケアラーについての説明を引用すると、ヤングケアラーとは、「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子ども」のことをいいます。
*参照 厚生労働省 ヤングケアラーについて (mhlw.go.jp)
「ケア」と一言に言っても身体的な介護や看護に限らず、幼いきょうだいのお世話だったり、家計を支えるための労働などもこれに当たります。
家族のケアのために、子どもが本来のその年齢に見合った子どもらしい生活が送れず、学校にも行けず、まして支援を求めることすら出来ずにいるということは、本当に早急な課題であると思います。
一人の家族介護の当事者として、福祉に携わる社会福祉士として、これらを「早急な課題である」と捉え、動き出すことは当然支持します。
ただ、どうしてもモヤモヤすることがあります。
それは、「ヤング(子ども)ケアラー」の「今」に特化した支援への視点が置かれすぎると、もしかしたらそれは将来的には危険かもしれないということです。
ヤングケアラーたちの家族介護は18歳で終わりですか?
ケアラー支援条例が制定されることは、賛成です。
早く、全国的に広がればいいと思いますし、目指すところは都道府県単位ではなく、さらにその先の市町単位での制定であるとも思い、今からとても強く願っています。
(このあたりについては、後程おいおい・・・)
そして、何度も申しますが、当然のことながらヤングケアラーへの支援も大賛成です。
では、されどモヤモヤとは何か?
「ヤングケアラーのあの子たちだって、そのうち大人になる。」ということです。
18歳じゃなくなります。
19歳、二十歳になります。
当たり前ですけど、成人し大人になっていくのです。
そして、もちろん個人差、事案差はありますが、彼らが今抱えている境遇や環境を考えれば、18歳から19歳になったときも、往々にして彼らが抱えているケアは続いている可能性の方が高いです。
万が一にでも、その頃のタイミングで家族へのケアが終わっていたとしても、彼らの人生において、ケアラーであった事実はなくなりません。
大きく「ケアラー支援」を考えること
「福祉」を生業にして二十数年・・・
制度化、法制化のデメリットをあげるとしたら、制度に法律に「区切られてしまうこと」だと思っています。
高齢者福祉も、障がい福祉も、児童福祉も・・・、制度化、法制化されるたびに当事者は半ば一方的に「区切られて」きました。
もちろん、そうしなければ収集がつかない事態になり得ることもあるのかも知れません。
ただ、当事者にしてみれば、自身の人生の中で、生活の中で、ずっと繋がっていることなのです。
当事者にとっては、介護も障がいも、何らかの生きづらさも、人生や生活の中にありますから。
19歳になったから、65歳になったから、昨日と変わっているわけないじゃないですか。
ケアラー支援を考えるとき、細かな支援内容としてヤングケアラーとおとなケアラー(19歳以上のケアラー)を分けて捉えることはあるかも知れません。
ただ、少なくとも我が国の今の段階で、行政がどちらか一方の支援に力を入れ、それで支援体制の構築ができたと満足されることがあるとすれば、それはおかしいと思います。
とても危険です。
ヤングケアラーの彼らが大人になり、社会人として自立する頃、世の中にまだ「介護離職問題」がはびこっていたら本末転倒ではないですか?
大人になった彼らに、再び別の苦労をさせますか?
19歳になった途端、自己責任だと彼らに言うのですか?
ヤングだろうが、大人だろうが、ケアラーはケアラーであり、「ケアラー支援」はあくまで一括りであるべきだと思います。
つまり、どの年代へのケアラー支援の体制整備も、並行して進められて欲しいのです。