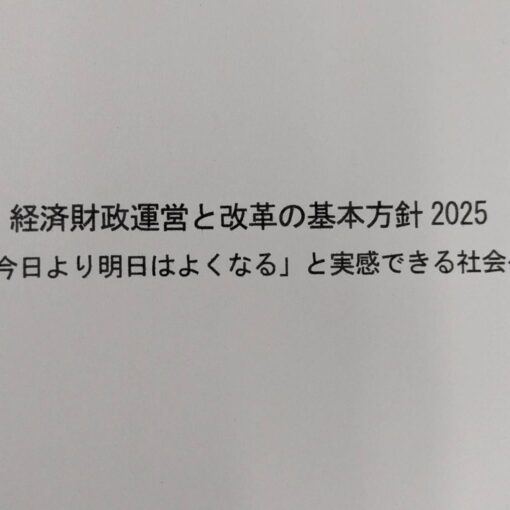専門職後見人がついたら
前回のブログで、要介護者である家族が「成年後見制度」を利用する場合の、特に「意思決定支援」に関するメリットを私なりに解説しました。
特に、家族介護者が本人に代わって求められる「重要な決断をすること」またその「精神的負担」について。
もし、要介護者である家族が成年後見制度を利用し、親族ではなく、第三者である専門職が後見人になったら。
当然のことながら、本人に対する意思決定支援はしてくれますし、預貯金等の管理も基本的に行います。
基本的にというのは、夫や妻などの配偶者がいても、子どもがいても、家庭裁判所が出した審判で、その業務内容に「預貯金等の管理」の項目が入っていれば、家族がいても対応しますということです。
ちなみに、私はこの項目が入っていない審判を見たことがありません。(類型が「後見」でしたら、必ず入っています。)
ある意味、審判の内容から職権を持ちますし、管理責任もあります。
自身が担うその責任を無視して、そうする根拠もないのに家族だからといって、丸々ポイっと別の人物に預けたりはしません。
その資産は誰の名義か
後見業務において重要なポイントは、審判の内容(仕事として決められた業務内容)と、それが本人(被後見人等)の名義かどうかです。
預貯金にしろ、土地家屋にしろ、それが誰の名義かということは重要になります。
ちょっと、余計な話をすると、負の財産(借金など)についてもそうです。
なので、先でも申しましたように、家族がいても業務上お預かりすべきものは預かりますし、他の家族が、その業務をまかされている後見人等に無断で、本人名義の資産を扱うことはできません。
この仕事をしていて、ときどきお聞きするのですが、特に家族介護者さんからは、「家族なのに。」とか、「妻(夫)なのに。」とか、「一緒に住んでるのに。」とか、いろいろなご意見を伺います。
そうですね。
言われているお気持ちは理解します。
ただ、そのもの(お金、家、土地、何某の貴重品など)が、誰のものであって、誰の名義かどうかというのは、誰に代わってそれを守るかという上で、明確にしなければこの業務(制度)はいささか成り立ちません。
守るべきものが守れず、その加減も状況次第で曖昧になります。
そして、この成年後見制度があくまで制度を利用されている被後見人等本人、「個人」のためにあることが基本だからです。
個人であって、でも家族でもあって・・・
そうは言いましても、なんだか解せないでしょう?
これらの手段は、たとえば金銭搾取など経済的虐待のからむ案件への対応としては、絶対的な効力を発揮します。
でも、多くの家族介護者さんが金銭搾取をしているわけではもちろんありません。
一生懸命夫婦で働いてきて、ただ、夫婦の一人がたまたま判断能力に支障が出る病気になって、いろいろな諸手続きのために必要だと言われてこの制度利用したのに・・・
その途端、後見人っていうまったくの他人が、「本人さんの通帳ですから。」と言って持っていった・・・なんてことになったら、それははがゆいですよね。
ニンゲンの感情として、当然だと思います。
誤解されがちなこの預貯金の管理について、大切なことを補足します。
本来、本人の名義である例えば年金とか、預貯金とか、そういった資産を、本人の介護や医療、生活のために活用することは当然です。
しかしながら、我々の生活や家庭の中には「義務」もあります。
夫婦で一人の生活がご自身だけではままならない状況の場合、例え後見人がもう一人の資産を管理していても、本来、被後見人本人が扶養する義務があり、またそれができる状況であれば、後見人はその配偶者の方の経済状況も考えなければいけません。
預かっているお金から、不足する分をお渡しすることも当然あります。
未成年の子がいたら、もちろん子への義務も発生します。
要は、本人が成年後見制度を今たまたま利用しているけど、家族の一員として、家庭の中で、どんな義務が生じているか?・・・ということです。
お金の管理のことでお話すると、もう一つ。
何度も言うように、その使途は「本人のため」であることが基本ですが、ここで身上の保護(監護)の視点を入れて、本来、本人がやりたかったことではないか・・・という考えのもと、それを本人に代わって代行することもあります。
私は、本人が病気した後に生まれたお孫ちゃんに、本人の預貯金からランドセルを買ってあげたことがあります。
本人が病気する前に生まれていた上の二人のお孫ちゃんのときに、本人がそうしてあげていたように、病気した後から生まれたその子にもお祝いとして贈りました。
もちろん、ここに至るまでには、後見人として本人に対してしっかりとしたアセスメントが必要ですし、想いを察することや、そもそも監督している家庭裁判所にその心情を本人に代わって訴え許可をもらうことも必要です。
これには、専門職後見人として、それぞれに意見は分かれるかも知れません。
ただ、「本人だったら・・・。」の想いを形にすることも、我々の仕事の一つだと私は思っています。
後見人等に支払う報酬
最後に、後見業務における報酬についてお話します。
後見報酬は、原則としてお預かりしている本人の預貯金から頂きます。
配偶者、子ども、他の親族に請求することはありません。
また、報酬額は、監督している家庭裁判所が決定します。
金額については、本人の持っている資産(現金)の額と、業務内容から決められます。
後見人の報酬は高額だと勘違いされがちなのですが、後見人等が報酬を頂くことで、今後の本人の介護費や医療費、生活費に支障がある金額になることはありません。
言わば、お金のない本人からはもらえないのが後見報酬です。
一年間、12か月まるまるしっかり働いて、報酬額が1,000円だってこともあり得ます。
ウソのような、本当の話です。
じゃあ、報酬支払えない人の業務なんて、誰も請け負ってくれないじゃないか!ってことになるかも知れませんね。
そのためにあるのが、市町の「報酬助成」という制度です。
本人が支払いが難しい場合の報酬を、市町から支援してもらう制度です。
市町によって要綱の内容は異なりますが、国はもう何年も前から都道府県や市町にこの制度整備を推進していますし、適切な、必要な後見活動(制度利用)のためにも必須だと思います。
ですので、「報酬支払えないから制度利用できない。」なんて、一ミリも考える必要はありません。(←このあたりの制度利用については、またおいおい・・・)
ちなみに・・・
後見報酬は、たとえば親族後見人でも申立(請求)することはできます。
たまに、「親族後見の人は無償だ。」とか、「家族なのにお金取るなんて。」とか、そんなご意見も耳にしますが、報酬申立ての権利があるかないかで言えば、しっかりあります。
家庭裁判所も「もらってはいけない。」なんて、まさか言いません。
「報酬をもらわないで業務してる。」人が、おそらく専門職後見人より多いだけです。
なんと言いますか、これは私の個人的な感触ですが、家族や家庭、親きょうだいとか、そういった集まりに対する日本人的な感覚や文化的な背景からくる価値観が、親族としての「美徳」みたいに言われ続けているのかと思います。
もちろん、考え方はいろいろですけども、私は、もし家族介護者さんが親族後見人も担う場合、報酬をあえて受け取ることは、どこか精神的な折り合いが付けやすくなることもあるのではないかと思い、むしろお勧めします。
それだけのことを、あなたは背負ってますよ。
家族介護者が、なかなか自分自身では見えなくなる部分かも知れません。